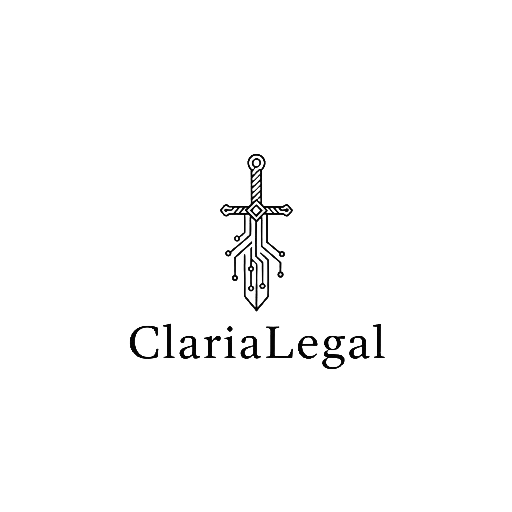相続事件は非常に大変です。
下記のような相続人の調査、相続財産の調査、紛争がある場合の対応を含めて全て弁護士にお任せいただいた方が、手間がかからず安心です。
第1 相続人の範囲の調査
1. 相続人の優先順位
相続人には法律上の優先順位があり、以下のルールに従って決定されます。
• 配偶者: 常に相続人となります。なお、最優先順位の相続人と同順位になります。
• 血族相続人: 以下の順位で、先の順位の者がいない場合にのみ後順位の者が相続人になります。
◦ 第1順位:子
◦ 第2順位:直系尊属
◦ 第3順位:兄弟姉妹
2. 特殊なケースにおける相続権
• 代襲相続: 本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡、相続欠格、または廃除によって相続権を失っている場合、その者の子が代わって相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)で、再代襲は認められません。
• 養子: 養子縁組をした子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、実子と同様に相続人となります。
• 胎児: 胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、相続人の範囲に含まれます。ただし、死体で生まれた場合には適用されません。
• 継子(連れ子): 被相続人の再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない限り相続人にはなれません。
3. 相続権の喪失
以下の場合、本来相続人となるべき立場であっても相続人の範囲から除外されます。
• 相続欠格: 遺言書の偽造・破棄・隠匿や、被相続人への殺害・殺害未遂などの不正行為を行った者は、法律上当然に相続権を失います。
• 推定相続人の廃除: 被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合、被相続人が家庭裁判所に請求し、認められれば相続権を剥奪できます。
• 相続放棄: 家庭裁判所に相続放棄の申述をした者は、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。
4. 所在不明者・外国籍の場合
• 行方不明者: 相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任するか、失踪宣告の手続きを経て遺産分割を進めることになります。
• 渉外相続: 被相続人が外国籍の場合、原則として被相続人の本国法に従って相続人の範囲や順位が決定されます。
5. 相続人の調査方法
相続人の範囲を正確に確定させるためには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、隠れた相続人がいないか調査する必要があります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍も必要となります。
相続人調査チェックリスト
1. 被相続人(亡くなった方)の基本調査
• [ ] 出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を連続して取得したか。※転籍や改製(法改正による作り替え)を辿り、空白期間がないように収集する必要があります。
• [ ] 住民票の除票または戸籍の附票を取得し、最後の住所地と本籍地の整合性を確認したか。
• [ ] 婚姻・離婚の履歴を確認し、前婚の間に生まれた子がいないか調査したか。
• [ ] 認知した子(婚外子)がいないか、父親の戸籍を確認したか。
• [ ] 養子縁組をしている、あるいは養子に出した子がいないか確認したか。
2. 血族相続人の優先順位と範囲の確認
• [ ] 配偶者(常に相続人)の有無を確認したか。
• [ ] 第1順位(子)がいるか確認したか。
◦ [ ] 子が亡くなっている場合、代襲相続人(孫・ひ孫)の有無を確認したか。
◦ [ ] 胎児がいるか確認したか(既に生まれたものとみなされます)。
• [ ] 第2順位(直系尊属):子がいない場合、父母や祖父母が存命か確認したか。
• [ ] 第3順位(兄弟姉妹):第1・第2順位がいない場合、兄弟姉妹の有無を確認したか。
◦ [ ] 兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続人(甥・姪)を確認したか(代襲は一代限りです)。
◦ [ ] 兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を取得したか。
3. 相続権の喪失・所在不明の確認
• [ ] 相続放棄をした者がいないか(「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます)。
• [ ] 相続欠格や推定相続人の廃除により、相続権を失った者はいないか。
• [ ] 行方不明(生死不明)の相続人がいないか。いる場合は不在者財産管理人の選任などを検討したか。
4. 特殊なケースの確認
• [ ] 渉外相続:被相続人が外国籍の場合、本国法に従って範囲を調査したか。
調査にあたっての留意事項
• 戸籍の広域交付制度(2024年3月開始):本人や配偶者、直系親族の戸籍は、最寄りの役所窓口でまとめて取得可能になりましたが、兄弟姉妹や甥姪の分は従来通り本籍地への請求が必要です。
• 再代襲の制限:兄弟姉妹が相続人の場合、その子が亡くなっていても、孫(姪孫)への再代襲は認められません。
• 数次相続の発生:遺産分割未了の間に相続人が亡くなった場合、その相続人の地位を引き継ぐ者を特定するためにさらに調査が必要です。
。
第2 相続財産の調査
相続財産の調査は、相続人が「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択するための重要な前提作業であり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間内に十分に行う必要があります。
1. 自宅の捜索(家捜し)と郵便物の確認
最も直接的かつ初めに行うべき方法は、被相続人の自宅に残された手がかりを捜索することです。
• 保管品の確認: 自宅内にある預金通帳、キャッシュカード、証券会社からの郵送物、保険証券、権利証(登記済証)などを探します。
• 郵便物の精査: 被相続人宛てに届く郵便物から、取引のある金融機関、証券会社、保険会社、または債権者からの督促状などを特定できます。
• デジタル遺産の調査: パソコンやスマートフォンを探索し、インターネットバンキングやネット証券の利用、仮想通貨などの取引の有無について、メールでの通知がないか確認します。
2. 不動産の調査
被相続人が所有していた不動産を漏れなく特定する必要があります。
• 名寄帳(土地・家屋名寄帳)の取得: 被相続人の所有物件があると思われる市区町村の役所で「名寄帳」を請求すると、その自治体内で課税対象となっている不動産の一覧を把握でき、漏れを防ぐのに非常に便利です。
• 登記事項証明書の確認: 特定した不動産について、法務局で「登記事項証明書」を取得し、現在の所有名義や抵当権の設定状況を確認します。
• 固定資産税納税通知書: 自宅に届いている通知書からも所有不動産を特定できます。
3. 預貯金・有価証券の調査
金融資産の有無と正確な残高を確認します。
• 残高証明書と取引明細書の請求: 取引があると思われる銀行や証券会社の支店窓口に対し、相続開始時点での残高証明書や、一定期間の取引明細書(取引履歴)を請求します。これらは相続人であれば単独で請求可能です。
• 出資証券の確認: 信用金庫や農業協同組合(JA)などでは、預金以外に「出資金」があることが多いため、併せて調査します。
4. 借金・債務の調査(消極財産)
相続放棄を検討する場合、マイナスの財産の調査は不可欠です。
• 信用情報機関への照会: 被相続人がカードローンやクレジットカードを利用していた可能性がある場合、CICやJICC、KSCなどの3信用情報機関に照会請求を行うことで、負債の有無や残高を確認できます。
• 契約書・督促状の確認: 自宅にある金銭消費貸借契約書や、個人債権者からの督促状を探します。
5. その他の専門的な調査方法
• 弁護士会照会: 相続人からの照会で支店や口座が特定できない場合でも、弁護士に依頼して弁護士会照会を利用することで、全店舗の口座を照会してくれる金融機関もあります。
• キーマンへのヒアリング: 同居していた親族や親密に交流していた知人など、財産状況を詳しく知っている可能性がある人物から情報を聞き取ります。
調査の結果、財産が多岐にわたり全容把握に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも検討すべきです。
各費目ごとの調査方法
1. 調査の基本アプローチ(手がかりの確保)
• 家探し(やさがし): 被相続人の自宅にある預金通帳、キャッシュカード、保険証券、権利証(登記識別情報通知)、郵便物、日記、メモなどを探し、財産の存在を推認させる資料を収集します。
• デジタル遺産の確認: 被相続人が使用していたパソコンやスマートフォンを探索し、ネットバンキング、ネット証券、仮想通貨などの利用状況を確認します。
• キーマンへのヒアリング: 被相続人と生前密に交流があった親族や知人から情報を収集します。
2. 各費目別の調査方法
① 不動産(土地・建物)
• 名寄帳(土地・家屋名寄帳)の取得: 自治体が作成している固定資産税の課税台帳で、当該市区町村内に被相続人が所有する不動産の一覧を確認できます。
• 登記事項証明書の確認: 最寄りの法務局で取得し、現在の所有権や抵当権の有無、共有持分などを特定します。
• 権利証・売買契約書: 自宅等に保管されているこれらの書類も有力な証拠となります。
• 固定資産税の納税通知書: 毎年届く通知書から、所有している物件の概要を把握できます。
② 預貯金・現金
• 残高証明書・取引明細の請求: 心当たりのある金融機関(支店・出張所等)に対して、相続開始時点での残高証明書や、過去の出入金を確認できる取引明細(取引履歴)の開示を求めます。
• 全店舗の照会: 弁護士会照会などを利用することで、支店が特定できない場合でも全店舗の口座を照会できる場合があります。
• 現金の保管状況: 自宅の金庫やタンス預金、また当事者が保管している現金の有無を確認します。
③ 有価証券(株式・投資信託)
• 証券会社等への照会: 預貯金と同様に、心当たりのある証券会社や信託銀行に取引残高報告書や顧客勘定元帳を請求します。
• 郵便物の確認: 証券会社からの通知書や、配当金の支払通知書などが届いていないか確認します。
④ 車両・動産
• 自動車: 自動車検査証(車検証)を確認し、登録番号、型式、所有者名義を特定します。
• 高額な動産: 美術品、貴金属、時計、骨董品など一点物の存在を確認します。
⑤ 生命保険・退職金
• 保険証券の確認: 自宅にある保険証券や、保険会社からの支払案内通知等を探します。
• 支給規定の確認: 被相続人の勤務先に、死亡退職金や弔慰金などの支給規定があるか確認します。
⑥ 消極財産(債務・借金)
• 信用情報機関への照会: カードローンやキャッシングの有無を確認するため、CICやJICC、KSCなどの信用情報機関に対して情報の開示請求を行います。
• 郵便物・通帳の確認: 督促状、契約書、通帳からの定期的かつ不自然な引き落としなどがないか確認します。
⑦ 遺言の有無
• 公証役場での検索: 1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場で有無を検索できます。
• 法務局での検索: 自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。
第3 遺言書の有無
相続において遺言書がある場合とない場合では、手続きの優先順位や進め方が大きく異なります。それぞれの主な流れは以下の通りです。
1. 遺言書がある場合の流れ
遺言書がある場合、原則として遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。
• 遺言書の捜索と検認:
◦ 自宅等で「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。ただし、2020年7月から始まった法務局での保管制度を利用している場合や「公正証書遺言」の場合は検認不要です。
• 遺言の有効性の確認:
◦ 署名・押印の有無、日付の特定、遺言能力(認知症の有無など)といった形式的・実質的な要件を満たしているか確認します。
• 遺言執行者の就職:
◦ 遺言で「遺言執行者」が指定されている場合、その者が遺産目録の作成や名義変更などの実務を単独で行うことができます。
• 財産の承継(名義変更):
◦ 遺言の記載(「相続させる」や「遺贈する」など)に基づき、不動産の登記や預貯金の払い戻し手続きを行います。
• 遺留分侵害額請求:
◦ 特定の相続人に全財産を譲るなどの内容で、他の法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合、侵害された相続人は受遺者らに対して金銭の支払いを請求することができます。
2. 遺言書がない場合の流れ
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)の間で話し合いによって分け方を決める必要があります。
• 相続人および相続財産の調査:
◦ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人を確定させます。
◦ 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も漏れなく調査します。
• 相続放棄・限定承認の検討:
◦ 借金が多い場合などは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申述を行う必要があります。
• 遺産分割協議:
◦ 相続人全員で、どの財産を誰がどのように引き継ぐかを話し合います。
◦ 合意に達した内容は「遺産分割協議書」にまとめ、全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。書面化は必須ではないものの、紛争防止の点からは確実に作成しましょう。
• 遺産分割調停・審判:
◦ 協議がまとまらない(争族になる)場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。
◦ 調停でも合意できない場合は審判手続きへ移行し、裁判官が法定相続分や諸般の事情を考慮して分割方法を決定します。
• 名義変更手続き:
◦ 成立した遺産分割協議書、または裁判所の調停調書・審判書を用いて、不動産や預貯金の名義変更を行います。
第4 遺言書の有効要件の確認
遺言書の「有効性」をチェックする
まず、その遺言書が法的に有効な要件を満たしているかを確認します。不備があれば、遺言そのものを無効と主張できる可能性があります。
• 形式的要件の確認(特に自筆証書遺言): 自筆証書遺言の場合、全文が自筆であるか、日付が特定されているか、署名・押印があるかといった厳格なルールがあり、これらを一つでも欠くと原則として無効になります。
• 遺言能力の有無: 遺言者が作成時に認知症などで遺言内容を理解し判断できる能力(遺言能力)を欠いていた場合、その遺言は無効となります。医療記録や介護記録、長谷川式認知症スケールの点数などが判断材料となります。
• 内容の不備や不正: 内容が不明瞭で特定できない場合や、他人の詐欺・強迫によって書かされた場合、また公序良俗に反する内容である場合も無効の原因となります。
1. 全ての遺言に共通する基本要件
• [ ] 遺言者が作成時に15歳以上であったか(15歳未満が作成した遺言は無効となります)。
• [ ] 遺言能力(意思能力)があったか(認知症などで遺言内容を理解し結果を認識できる能力を欠いていた場合、無効になる可能性が高くなります)。
• [ ] 一人で作成されているか(夫婦連名など、2人以上の者が同一の証書でする「共同遺言」は禁止されており無効です)。
• [ ] 内容が明確(特定可能)か(誰にどの財産を渡すのか、第三者が客観的に判断できる必要があります)。
• [ ] 公序良俗に違反していないか(社会常識に反する不当な内容は無効となる場合があります)。
• [ ] 詐欺や強迫によるものではないか(他人の不正な干渉により作成された意思表示には瑕疵があり、取り消される可能性があります)。
• [ ] 最新の遺言書であるか(内容が矛盾する複数の遺言がある場合、日付が最も新しいものが優先され、古いものは無効となります)。
——————————————————————————–
2. 自筆証書遺言の形式要件
自筆証書遺言は民法968条により厳格な方式が定められており、一つでも欠けると原則として遺言全体が無効になります。
• [ ] 全文が自筆で書かれているか(財産目録を除き、パソコン作成や代筆、録音・録画によるものは無効です)。
• [ ] 具体的な日付が特定できるか(「令和〇年〇月吉日」のように日が特定できない記載は無効です)。
• [ ] 氏名が自書されているか(氏または名のいずれか、あるいは通称でも本人との同一性が認められれば有効とされます)。
• [ ] 押印がされているか(実印でなくてもよく、認印や指印でも有効ですが、押印がない場合は無効になります)。
• [ ] 財産目録を自書以外(パソコン等)で作成した場合、全てのページに署名・押印があるか(裏面にも記載がある場合は両面に必要です)。
• [ ] 訂正・加筆が正しい方式で行われているか(訂正箇所に押印し、欄外等に「〇字削除、〇字加入」と記載して署名する必要があります。修正テープ等の使用は無効の原因となります)。
——————————————————————————–
3. 公正証書遺言の形式要件
公正証書遺言は公証人が作成するため形式不備は少ないですが、以下の立会人等の要件が重要です。
• [ ] 証人2人以上の立ち会いがあったか(証人は作成の最初から最後まで立ち会う必要があります)。
• [ ] 証人になれない者(欠格者)が含まれていなかったか(未成年者、推定相続人、受遺者、およびそれらの配偶者や直系血族などは証人になれません)。
• [ ] 遺言者が公証人に内容を「口授」したか(公証人の質問に対し単に頷くだけでは口授とは認められない場合があります)。
——————————————————————————–
第5 遺言の争い方
1. 遺言の無効を裁判所で争う
遺言の有効性に疑いがあるが、相続人間で意見がまとまらない場合は、法的な手続きをとります。
• 遺言無効確認調停: 家庭裁判所に申し立て、調停委員を交えて遺言の有効性について話し合います。遺言無効を争う場合は、まずこの調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。
• 遺言無効確認訴訟: 調停で解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起します。裁判所が遺言を無効と判断すれば、遺言書はなかったものとして「遺産分割協議」へ移行します。
2. 相続人全員の合意で「遺産分割協議」を行う
遺言書が有効であっても、相続人(および受遺者)の全員が合意すれば、遺言の内容に従わずに、話し合いで全く別の分け方を決めることができます。 ただし、一人でも反対する者がいれば、遺言の内容が優先されます。
3. 「遺留分侵害額請求」を行う
遺言書が有効であり、他の相続人との合意も困難な場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」があります。
• 請求の内容: 遺言によって遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、遺産を多く受け取った人(受遺者や受贈者)に対して、侵害された額を金銭で支払うよう請求できます。
• 期限に注意: この請求は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈などを知った時から1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると時効により権利が消滅するため、実務上は内容証明郵便などで意思表示を行います。
• 手続きの流れ: 当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
4. 遺言の解釈や前提問題を整理する
遺言の文言が不明確な場合や、遺言に記載されていない財産(未分割遺産)がある場合は、その点について調停の場で調整を図ることができます。
• 一部分割の検討: 争いがない財産だけを先に分け、納得できない部分(遺留分や遺言の解釈が分かれる部分)を後から協議することも可能です。
納得できない遺言が見つかった際は、まずはその遺言が形式・能力の両面で有効かを精査し、その上で遺留分の侵害がないかを確認することが、解決に向けた具体的な第一歩となります。
コラム録音録画について
遺言能力を証明するための録画や録音は、「遺言が有効であることを補強する客観的な証拠」として非常に有効です。ただし、録音や録画そのものが「遺言書」としての法的効力を持つわけではない点に注意が必要です。
1. 遺言能力を証明する証拠としての有効性
遺言能力とは、遺言者が内容を理解し、その結果を認識できる能力を指します。
• 作成状況の記録: 遺言書を作成する際の様子を録画・録音しておくことで、本人が自分の意思で話しているか、内容を正しく理解しているかを後から客観的に確認できるため、有効性を主張する際の有力な証拠となります,。
• 行動観察の記録: 専門医が遺言能力を判断する際にも、当時の症状や言動の記録は「行動観察的観点」からの重要な材料として扱われます。
2. 録画・録音の限界と注意点
録画や録音はあくまで「証拠」であり、日本の法律では録音・録画のみによる遺言(方式)は認められていません。
• 方式の不備: 自筆証書遺言の場合、録音データは「自書(本人の手書き)」の要件を満たさないため、それ自体で遺言が成立することはありません。
• 公正証書遺言の補完: 公正証書遺言を作成する際に録画を残しておくことは、公証人の前で正しく「口授(内容を口頭で伝えること)」が行われたことを証明する一助になります,。
3. より確実な証明のために
認知症の疑いがあるなど遺言能力に不安がある場合、録画に加えて以下の対応をとることが推奨されています。
• 生前遺言能力鑑定の受診: 認知症専門医に作成時の遺言能力を医学的に評価してもらい、その鑑定結果を残しておくことで、将来的な紛争リスクを大幅に抑えることができます。
• 医療・介護記録の併用: 医師の診断書、長谷川式認知症スケールの点数、カルテ、看護記録なども併せて保管しておくことが、総合的な判断において有効です,。
まとめると、録画や録音は作成時の本人の状態を証明する「証拠資料」として活用すべきであり、法的に有効な形式(自筆証書や公正証書など)の遺言書を別途作成することが不可欠です。
第6 遺言書の有効性を争う場合に収集すべき資料
1. 遺言能力(認知症等の影響)を争うための証拠
遺言者が内容を理解し、判断できる状態であったかを確認するために、以下の資料が有力な証拠となります。
• 医療記録(カルテ等): 病院での診療録(カルテ)、MRIやCTなどの画像検査結果は非常に重要です。
• 認知機能テストの結果: 「長谷川式認知症スケール」や「MMSE」の点数は、当時の判断能力を示す直接的な指標となります。
• 介護記録・看護記録: 施設や病院での様子を継続的に記録した看護記録、介護日誌、ケアプランなどは、日常生活での行動観察の証拠になります。
• 介護保険の認定調査票: 介護保険を申請した際の調査書には、当時の心身の状態が詳しく記載されています。
• 本人の日記やメモ: 遺言書作成と同時期の日常的な記述内容から、つじつまが合っているか、記憶が確かかを確認します。
2. 自筆証書遺言の自筆性(偽造の疑い)を争うための証拠
遺言書が本当に本人の手で書かれたものかを確認するために、比較対象となる資料が必要です。
• 筆跡比較のための資料: 遺言書作成時期に近い、本人が書いた日記、メモ、手紙、年賀状などを可能な限り多数収集します。
• 筆跡鑑定: 集めた資料をもとに、専門家による筆跡鑑定を行うことが検討されます。
• 保管・発見の状況に関する説明: 遺言書がどこに保管され、どのような経緯で誰が発見したのかという関係者の説明に不自然な点がないかも判断材料となります。
3. 公正証書遺言の作成過程を争うための証拠
公証人が作成する公正証書遺言であっても、本人の意思が反映されていない(口授がない)などの疑いがある場合は、以下の調査が必要です。
• 証人・立会人等への聴取: 作成時に立ち会った証人や公証人、親族などから、作成当時の状況(公証人の質問に単に頷いただけではないか等)を聞き取ります。
• 作成前の意向を示す資料: 遺言作成に至る経緯や動機を裏付ける、本人の事前のメモなどがあるか確認します。
証拠収集の方法
• 文書送付嘱託: 訴訟や調停の手続きの中で、裁判所を通じて病院などから医療情報を開示させることが可能です。
• 遺言能力鑑定: 専門医に依頼し、診療録や検査結果を精査して遺言能力を評価してもらう選択肢もあります。
遺言書の内容に納得がいかない場合は、まずこれらの資料を精査し、形式面(署名・押印・日付など)と実質面(遺言能力など)の両面から有効性を確認することが解決への第一歩となります。
病院のカルテや医療記録を証拠として開示させるための具体的な手順と方法
1. 手続きの前提:遺言無効確認訴訟など
遺言者の認知症等による「遺言能力」の有無を争う場合、病院のカルテ、MRI・CTなどの画像検査結果、知能検査(長谷川式スケールやMMSE)の点数が極めて重要な証拠となります。これらの資料を公式に取得するためには、裁判手続きの中で証拠調べを申し立てる必要があります。
2. 具体的な開示請求の手順
裁判所を通じて医療情報を開示させるには、主に以下の方法が用いられます。
• 文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく): 訴訟手続きにおいて、裁判所を通じて病院などの文書保持者に対し、医療情報の開示や文書の送付を求める方法です。遺言能力が争点となる事案では、この方法で遺言者の入院先からカルテ等の送付を求め、提出された文書を証拠とすることが一般的です。
• 調査嘱託(ちょうさしょくたく): 裁判所が官公署や病院などの団体に対して、必要な調査を依頼し、報告を求める手続きです。
• 遺言能力鑑定: 専門医に依頼し、診療録(カルテ)や検査結果、介護保険の認定調査票などを精査して、当時の遺言能力を医学的に評価してもらう方法もあります。この鑑定報告書も裁判所での重要な証拠となります。
3. 収集すべき対象資料の例
カルテを開示させる際、併せて以下の資料も証拠として検討されます。
• 診療録(カルテ)入院診療録。
• 看護記録・介護記録:病院や施設での日常の様子が継続的に記録されており、行動観察の証拠になります。
• 長谷川式認知症スケール等の検査結果:当時の認知機能の程度を客観的に示す指標となります。
• 介護保険の認定調査票:自治体が作成するもので、心身の状態が詳しく記載されています。
これらの資料は、個人が病院に請求しても開示を拒まれるケースがあるため、遺言無効確認調停や訴訟の中で、裁判所の権限を利用して収集することが実務上の確実な手段となります。
第7 遺留分侵害額請求の流れと期限
遺留分侵害額請求の期限と具体的な手続きは、以下の通りです。
1. 請求の期限(消滅時効と除斥期間)
遺留分侵害額請求権には厳格な期限があり、これを過ぎると権利が消滅します。
• 消滅時効:相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。
• 除斥期間:相続開始の時から10年を経過したときも、同様に権利が消滅します。
2. 具体的な手続きの流れ
手続きは原則として「意思表示」「調停」「訴訟」の順に進みます。
① 相手方への意思表示
遺留分侵害額請求を行うには、まず贈与や遺贈を受けた相手方に対して、権利を行使する旨の意思表示をする必要があります。
• 内容証明郵便の利用:家庭裁判所への調停申し立てだけでは時効を止める意思表示とはみなされないため、別途配達証明付内容証明郵便などで通知を行い、証拠を残すことが実務上不可欠です。
• 請求の相手方:原則として、遺留分を侵害している受遺者(遺言で財産をもらった人)や受贈者(生前贈与を受けた人)です。受遺者と受贈者の両方がいる場合は、まず受遺者が先に負担します。
② 遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所)
当事者間での話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。遺留分侵害額請求については、訴訟の前にまず調停を行う必要がある調停前置主義が採用されています,。
• 申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
• 費用:対象者1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代が必要です。
• 必要書類:申立書のほか、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写し、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書や残高証明書など)が必要です。
③ 遺留分侵害額請求訴訟(地方裁判所)
調停で合意に至らなかった場合は、最終的に民事訴訟を提起して解決を図ります。
• 管轄:被告(相手方)の住所地を管轄する地方裁判所となります。
• 内容:現行法では、遺留分の行使によって生じる権利は金銭債権とされており、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることになります。
3. 侵害額の算定方法
算定の基礎となる財産の価額に遺留分割合を乗じ、そこから遺留分権利者が相続によって取得した財産額を控除し、承継した債務額を加算して算出します。 評価の基準時は、原則として遺産分割時(調停・審判時)の時価となります。
遺留分を侵害する「遺贈」と「贈与」が複数ある場合の負担順序(請求相手の優先順位)
1. 遺贈と贈与の優先順位
遺贈(遺言による財産の譲渡)と贈与(生前贈与)の両方がある場合、遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担します。 受遺者が負担してもなお遺留分侵害額に満たない場合に、初めて贈与を受けた人(受贈者)が負担することになります。
2. 複数の遺贈がある場合の優先順位
遺言によって遺産を受け取った人が複数いる場合、負担の順序は以下の通りです。
• 原則(案分負担): 各受遺者が、それぞれの遺贈の目的の価額の割合に応じて負担します。
• 例外(遺言による指定): 遺言者が遺言の中で負担の順序を別途指定していた場合は、その意思が優先されます。
• 相続分の指定等: 遺言による「相続分の指定」や「特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)」によって財産を得た人も、特定の遺贈を受けた人と同順位で負担します。
3. 複数の贈与がある場合の優先順位
生前贈与を受けた人が複数いる場合、前の贈与ほど法律関係の安定を保護する必要があるため、以下の順序で負担します。
• 新しい贈与が優先: 日付が後の贈与(新しいもの)の受贈者から順に負担し、順次、前の贈与(古いもの)の受贈者へと遡っていきます。
• 同時期の贈与: 複数の贈与が同時に行われた(同一日付など)場合は、遺贈と同様に価額の割合に応じて案分して負担します。
4. 死因贈与の扱い
死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)は、その性質上、遺贈に関する規定が準用されます。 そのため、負担の順序についても原則として遺贈と同順位(あるいは遺贈に次いで、生前贈与よりは先に負担する順位)として扱われます。
注意点
遺留分侵害額の請求は金銭債権であるため、相手方は侵害額に相当する金銭を支払う義務を負いますが、直ちに金銭を準備することが困難な場合には、裁判所に対し支払いの期限の猶予(許与)を求めることができます。
遺留分の算定方法および具体的相続分における特別受益の扱いについて
1. 遺留分算定の基礎となる財産額(算定基礎額)
遺留分を計算するための基礎となる財産額は、以下の算式によって算出されます。
算定基礎額 =(相続開始時の財産 + 贈与財産 - 相続債務の全額)
このうち「贈与財産」として持ち戻し(加算)ができる範囲については、法改正により以下のルールが定められています。
• 相続人に対する贈与(特別受益): 原則として、相続開始前の10年以内になされたもの(婚姻、養子縁組、または生計の資本として受けたもの)に限定されます。
• 第三者に対する贈与: 相続開始前の1年以内になされたものが対象です。
• ※ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、期間の制限なく加算されます。
2. 具体的相続分と特別受益の差し引き
遺留分権利者が、実際にいくら請求できるか(遺留分侵害額)を計算する際には、本人の「具体的相続分」を考慮する必要があります。具体的相続分は、算定基礎額をベースに以下のように算出されます。
• 具体的相続分の計算: 遺留分の算定基礎額(総相続財産に10年以内の贈与を持ち戻した額)に、各相続人の法定相続分を乗じた額から、「自分(請求者本人)が受けた特別受益の額」を差し引いたものが、その人の具体的な取り分となります。
• 10年以内かどうかの区別: 算定基礎額に「加算」して全体のパイを大きくできる贈与は「10年以内」という制限がありますが、相続人間での公平を図るという観点から、請求者本人が過去に得た受益を差し引く際には、10年前かどうかにかかわらず、本人が受けた特別受益の額が考慮(控除)されることになります。
3. 遺留分侵害額の最終的な算定
最終的に相手方に請求できる「遺留分侵害額」は、以下のステップで導き出されます。
1. 遺留分額(算定基礎額 × 遺留分割合)を算出する。
2. そこから、具体的相続分(本人が相続によって取得する財産額から、10年以内かに関わらず受けていた本人の特別受益額などを差し引いた額)を控除する。
3. 本人が負担すべき相続債務額を加算する。
このように、算定基礎額(全体のパイ)を計算する際の持ち戻しは「10年以内」という期間制限がありますが、個々の相続人が既に得た利益を清算して不公平をなくすための差し引きにおいては、過去の特別受益が広く考慮される仕組みとなっています。
第8 遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、主に、遺言書がない場合に相続人全員の間で行われます。
1. 前提条件の調査と確定
協議を始める前に、客観的な資料に基づいて以下の2点を確定させる必要があります。
• 相続人の確定: 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、隠れた相続人がいないか調査します。一人でも欠けた協議は無効となります。
• 遺産の調査と特定: 不動産(土地・建物)、預貯金、株式、現金などのプラスの財産をリストアップし、遺産目録を作成します。
2. 遺産分割協議の進め方(段階的進行モデル)
家庭裁判所の調停でも採用されている「段階的進行モデル」に沿って進めることが、感情的対立を避け、合理的な合意形成を図るために有効です。
• 第1段階:相続人の範囲の確認 前述の調査結果に基づき、誰が当事者であるかを全員で再確認します。
• 第2段階:遺産の範囲の確定 何が分割の対象となる遺産であるかを確定させます。
◦ 対象となるもの: 土地、建物、預貯金、株式、現金など。
◦ 対象外(合意が必要なもの): 相続開始後の賃料・利息、使途不明金、葬儀費用、相続債務など。これらは原則として対象外ですが、当事者全員が合意すれば協議に含めることができます。
• 第3段階:遺産の評価の確定 遺産の経済的価値を評価します。不動産などは評価基準時(原則は遺産分割時の時価)や評価方法について合意が必要です。
• 第4段階:具体的相続分の算定 法定相続分をベースに、「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分(介護などの貢献)」を考慮して、各相続人の最終的な取得額を調整します。
• 第5段階:分割方法の決定 誰がどの財産をどのような形で受け取るかを決めます。主な方法は以下の4つです。
1. 現物分割: 土地や建物をそのまま特定の人が引き継ぐ。
2. 代償分割: 財産を多くもらう人が、他の人に自分の金銭(代償金)を支払う。
3. 換価分割: 遺産を売却して現金化し、その代金を分ける。
4. 共有分割: 遺産をそのまま複数の相続人の共有名義にする。
3. 遺産分割協議書の作成
全員の合意が成立したら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
• 署名・押印: 相続人全員が署名し、実印で押印します。
• 印鑑登録証明書の添付: 登記手続きや銀行手続きの際に、実印であることを証明するために必要となります。
4. 協議がまとまらない場合
話し合いが成立しない、または話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きへ移行し、裁判官が分割方法を決定します。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されるため、遺産分割協議の対象とはなりません。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で分割することも可能です。
第9 遺産分割の対象となる財産か否か
現金
現金は、当然に遺産分割の対象となる財産です。
預貯金
現在の実務では、預貯金も当然に遺産分割の対象となります。
利息
相続開始後に発生した利息についても、預貯金本体とあわせて遺産分割の対象として処理するのが一般的です。
有価証券(株式・国債・投資信託)
有価証券は、預貯金と同様に遺産分割の対象となる財産です。これらは相続開始と同時に当然に分割されることはなく、協議や審判によって具体的に誰が引き継ぐかを決定します。
◦ 上場株式:原則として、遺産分割時(調停成立時や審判時)の直近の終値を基準に評価します,。
◦ 非上場株式:客観的な市場価格がないため、当事者間での合意や、専門家による査定、あるいは必要に応じて株価鑑定を実施して評価を確定させます。
配当金・利息
相続開始後に発生した株式の配当金や預貯金の利息も、原則として本体の財産とあわせて遺産分割の中で処理するのが一般的です。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産は、相続分割の対象となります。
評価の注意点:
◦ 価格変動が非常に激しいため、遺産の評価を確定する際には、どの時点の時価を採用するかについて当事者間での合意や慎重な検討が必要となります。
出資金
信用金庫や農業協同組合(JA)に預金がある場合、預金とは別に「出資金」が存在することが多く、これも分割対象となります。
投資信託
相続開始と同時に当然分割されることはない性質の財産であるため、遺産分割の対象に含まれます。評価額は口数や基準価額に基づいて算出します。
相続不動産の賃料(発生時期による違い)
賃料については、被相続人が亡くなった「死亡時」を境に、法律上の扱いが明確に分かれます。
死亡前に発生した賃料
被相続人が生前に取得していた権利であるため、当然に遺産分割の対象(遺産)となります。
死亡後に発生した賃料
原則: 相続開始から遺産分割が完了するまでの間に発生した賃料は、遺産とは別個の財産(遺産から生じた果実)とみなされます。判例では、これらは各相続人がその相続分に応じて確定的に取得するものであり、原則として遺産分割の対象には含まれないとされています,。
実務上の取扱い: ただし、不動産を取得した人が賃料もまとめて受け取る方が合理的であるため、相続人全員の合意があれば、遺産分割の中に含めて一緒に分けることが可能です。実際の調停などの現場では、清算の煩雑さを避けるために合意の上で分割対象に含めることが多く行われています。
生命保険金(死亡保険金)
• 原則: 受取人が指定されている場合、保険金請求権は受取人の固有財産であり、相続財産には含まれません。
• 受取人の指定がない場合: 多くの場合は保険約款に基づき遺族の固有財産となり、やはり相続財産にはならないのが一般的です。
• 相続放棄との関係: 生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄をした人であっても受け取ることが可能です。
• 特別な例外(特別受益): 他の相続人と比較して受取額が著しく高額で、不公平が到底容認できないほど大きい場合には、例外的に「特別受益(生前贈与に準ずるもの)」として持ち戻しの対象となることがあります。
遺族年金・遺族給付
• 原則: 遺族年金や遺族給付金は、残された遺族の生活保障を目的としたものであり、受給権者固有の財産です。
• 相続財産性: 被相続人の権利ではないため、相続財産には含まれません。
• 相続放棄との関係: 受給資格を持つ遺族であれば、相続放棄をしていても受け取ることができます。
未支給年金
• 原則: 本人が受け取る前に亡くなった年金(未支給年金)も、法律(国民年金法等)によって受給すべき遺族の順位が定められており、その遺族の固有財産とされます。
• 判断: 最高裁の判例でも、相続財産ではなく受取人の固有財産であると判断されています。
死亡退職金
• 原則: 就業規則や支給退職金規定などで受給権者が定められている場合、その受給権者の固有財産となり、相続財産には含まれません。規定の内容が重要なので、場合によっては相続財産になることもあります。
葬儀費用・香典
• 原則: 葬儀費用や香典は、相続開始後(死亡後)に発生するものであるため、原則として相続財産には含まれません。
• 負担の考え方: 葬儀費用は原則として喪主が負担する(香典返しがあるためです。)ものとされていますが、実務上は当事者全員の合意があれば遺産から精算することも可能です。
祭祀財産(墓石、仏壇など)
• 原則: 墓石、仏壇、系譜などの祭祀財産は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者が承継するため、一般の相続財産とは区別され、遺産分割の対象にはなりません。
第10 寄与分
1. 寄与分が認められる条件(相続人の場合)
寄与分が認められるには、単なる親族間の助け合いを超えた「特別な寄与」である必要があります。同居していなくても、以下の類型に該当すれば認められる可能性があります。
• 金銭出資型、扶養型: 同居していなくても、被相続人の生活費や医療費、老人ホームの費用などを継続的に負担し、被相続人の出費を抑えることで財産の維持に貢献した場合です。
• 家業従事型: 被相続人が営む自営業や農業を、離れた場所から通って無報酬または低賃金で手伝い、財産の維持・形成を助けた場合です。
• 財産管理型: 被相続人のアパートなどの賃貸物件を無償で管理し、管理費の支出を抑えたり収益を確保したりした場合です。
• 療養看護型(介護など): 被相続人が一人暮らしや施設入所をしていても、相続人が頻繁に通って本来必要だった付添費用や介護サービス費用を免れさせたといえるほどの献身的な介護を行っていれば、認められることがあります。
◦ ただし、単なる「施設への見舞い」程度では、財産上の維持・増加への貢献がないとみなされ、寄与分として認められるのは難しいとされています。
2. 相続人以外の親族による貢献(特別寄与料)
もし「同居親族がいない」状況で、相続人ではない親族(例:長男の妻や、叔父・叔母など)が一人暮らしの被相続人を支えていた場合、2019年の法改正で新設された「特別寄与料(とくべつきよりょう)」という制度を利用できます。
• 対象: 相続人ではない親族(親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します)。
• 内容: 被相続人の療養看護等を行い、無償で特別な貢献をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます。
• 条件: 相続人が請求する寄与分と同様、財産の維持または増加への貢献が必要です。
3. 注意点
• 精神的寄与の否定: 被相続人の話し相手になる、精神的な支えになるといった「精神的寄与」については、財産上の効果が認められないため、寄与分・特別寄与料ともに認められません。
• 期間の制限: 寄与分(相続人間の争い)の主張は、原則として相続開始から10年以内に行う必要があります。
寄与分がある場合の相続分の計算
具体的な計算方法と手順は以下の通りです。
1. みなし相続財産の算定
遺産分割の対象となる基礎となる財産(みなし相続財産)を求めます。
これは、相続開始時の財産価値から、特定の相続人の貢献分(寄与分)を差し引き、さらに生前贈与などの特別受益を加算することで算出します。
【計算式】 みなし相続財産 = 相続開始時の財産価額 + 特別受益の額 - 寄与分額
2. 具体的相続分の算定
算出した「みなし相続財産」に、それぞれの法定相続分(または指定相続分)を掛け合わせ、そこから個別の調整(寄与分の加算、特別受益の控除)を行います。
【計算式】 具体的相続分 =(みなし相続財産 × 相続分)+ 寄与分 - 特別受益
この計算により、寄与分が認められた相続人は、本来の相続分に加えて寄与分に相当する額を多く取得できることになります。
3. 寄与分額(寄与行為)の評価方法
具体的相続分を計算するための前提となる「寄与分額」は、その寄与の類型に応じて評価されます。
• 家業従事型: 本来支払われるべき給付額 × (1 - 生活費控除割合) × 寄与期間。
• 金銭出資型: 出資額(不動産の場合は相続開始時の価格)× 裁量割合。
• 療養看護型: 第三者に依頼した場合の報酬相当額 × 療養看護日数 × 裁量割合。
• 扶養型: 負担した扶養料の総額 × 裁量割合。
• 財産管理型: 第三者に依頼した場合の管理費用相当額 × 裁量割合。
4. 注意点
• 算定の基準時: 特別受益や寄与分の評価は、遺産分割時ではなく、原則として相続開始時の時価を基準として評価されます。
• 寄与分の上限: 寄与分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできません。
• 主張の制限: 相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として寄与分の主張による相続分の修正ができなくなるため注意が必要です。
第11 相続放棄
1. 相続財産の調査と検討(~1か月)
まず、プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、未払金など)がそれぞれどの程度あるかを調査します。
• 熟慮期間: 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。
• 法定単純承認の回避: この期間中に遺産を処分したり隠したりすると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、放棄ができなくなるため注意が必要です。
• 期間の伸長: 財産調査が3か月以内に終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長(伸長)できる場合があります。
2. 必要書類の準備(~2か月)
被相続人との関係性によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類を準備します。
• 相続放棄申述書: 家庭裁判所の窓口やWebサイトで入手可能です。
• 被相続人の住民票除票または戸籍附票: 最後の住所地を証明するために必要です。
• 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本: 死亡の事実を確認します。
• 申述人(放棄する人)の戸籍謄本: 相続人であることを証明します。 ※兄弟姉妹が放棄する場合などは、先順位者の生死を確認するための戸籍一式が追加で必要となり、収集に時間がかかることがあります。
3. 家庭裁判所への申し立て(~2か月半)
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
• 費用: 相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代が必要です。
• 提出方法: 窓口への持参、または郵送で提出します。
4. 照会書への回答
申し立てから約10日〜2週間後、裁判所から「照会書」(質問票)が届きます。
• 回答と返送: 放棄が本人の意思であるか、単純承認にあたる行為をしていないか等の質問に回答し、署名・押印して返送します。申述書の内容と矛盾がないよう注意が必要です。
5. 相続放棄の受理と通知
裁判所で受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
• 証明書の発行: 第三者に証明する必要がある場合(不動産登記や債権者への提示など)は、別途「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請できます。
6. 放棄完了後の対応
• 債権者への通知: 借金がある場合、債権者に通知書や証明書の写しを提示することで、支払義務がないことを示します。
• 次順位者への連絡: 放棄によって相続権が次順位の人(例:子が放棄した場合は親、親がいない場合は兄弟姉妹)に移行するため、トラブルを避けるために知らせておくことが推奨されます。
• 管理義務: 放棄をしても、次に管理を始める人が現れるまでは、占有している財産を保存・管理し続ける義務が残る場合があります。
ポイント・注意事項
1. 「3か月以内」の熟慮期間を厳守する
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、借金なども含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。
2. 「法定単純承認」に該当する行為を避ける
相続放棄を検討している間、あるいは申述をした後であっても、以下のような行為を行うと相続を承継したとみなされ、相続放棄ができなくなります(または無効になります)。
• 遺産の処分: 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使ったり、不動産の名義を変更したりする行為。
• 遺産の隠匿・消費: 相続財産を隠したり、勝手に消費したりする行為。
• ただし、社会通念上相当な額の葬儀費用を遺産から支払うことは、直ちに単純承認とはみなされない傾向にあります。
3. 一度受理されると「撤回」はできない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として後から撤回することはできません,。後になって「実はプラスの財産の方が多かった」と判明しても取り消せないため、事前の十分な財産調査が不可欠です,。
4. 次順位の相続人への影響とトラブル
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。その結果、相続権は次順位の者(親や兄弟姉妹など)へ移ります。マイナスの財産(借金)がある場合、それらも次順位者に引き継がれることになるため、あらかじめ他の親族に伝えておくなどの配慮がトラブル防止に繋がります。なお、相続放棄によって代襲相続は発生しません(放棄した人の子が代わって相続人になることはありません)。
5. 放棄後も「管理義務」が残る場合がある
相続放棄をしたからといって、直ちに一切の責任を免れるわけではありません。放棄の時に現に占有している相続財産がある場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定められています。
6. 相続放棄しても受け取れる財産
生命保険金などは、相続人自身の「固有の財産」とみなされるため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。
• 生命保険金(受取人が指定されている場合)
• 遺族年金・未支給年金, ただし、生命保険金などは税法上「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があり、相続放棄をした人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されない点には注意が必要です。