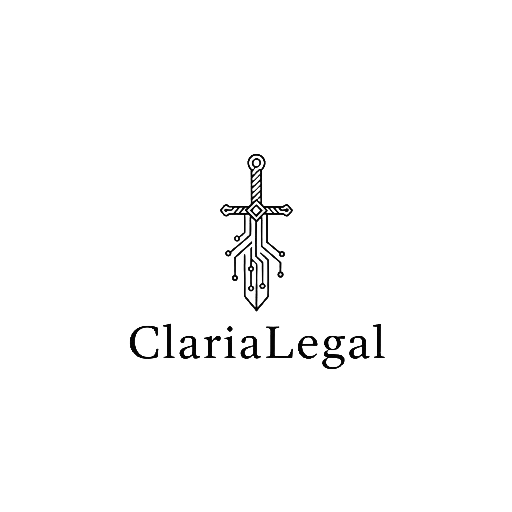交通事故で愛車が壊れてしまった…。「修理して乗り続けたい」と思っても、相手方の保険会社から「修理代の全額は払えません」と言われてしまうことがあります。これは「経済的全損(けいざいてきぜんそん)」というルールが関係しています。
なぜ修理代が全額支払われないことがあるのか、その場合いくら支払われるのか、そしてその金額はどうやって決まるのか。物損事故の賠償における重要なポイントを3つに分けて解説します。
1. 支払われるのは「時価額」か「修理費」の”低い方”
物損事故の賠償における大原則は、原状回復です。しかし、それは必ずしも「車を元通りに修理すること」を意味しません。
賠償は、事故直前の車両の時価額 + 買替諸費用(一部) + (車の売却代金)が上限とされています。そのため、保険会社は「修理費の見積額」と「事故直前の車両の時価額 + 買替諸費用(一部) + (車の売却代金)」を比較し、どちらか低い方の金額を賠償額として支払います。
この時、修理費が事故直前の車両の時価額 + 買替諸費用(一部) −(車の売却代金)を上回ってしまう状態を「経済的全損」と呼びます。
経済的全損の場合の計算方法
経済的全損と判断された場合、支払われる賠償額は修理費ではなく、以下の合計額となります。
賠償額 = 事故直前の車両の時価額 + 買替諸費用(一部) − (車の売却代金)
- 時価額: その車が事故に遭わなければ、中古車市場でいくらの価値があったかという金額です。
- 買替諸費用: 新たに同等の車を買い替えるために必要となる登録費用や車庫証明費用などの一部が、損害として認められる場合があります。
- 売却代金(スクラップ代): 事故で壊れ、これをスクラップ業者などに売却して得たお金は、賠償額から差し引かれます。
- なぜ差し引くのか?もしスクラップ代を差し引かずに、加害者が「時価額+買替諸費用」の全額を賠償金として支払ってしまうと、被害者は賠償金とスクラップ代の両方を手に入れることになります。そうなると、事故がなければ得られなかったはずの「スクラップ代」分の利益が余分に発生し、被害者が事故前よりも経済的に得をしてしまう可能性があります。これを「利得の禁止」の観点から防ぐために、スクラップ代は賠償額から差し引かれるのです。
例えば、愛車の時価額が50万円、買い替え諸費用が5万円、スクラップ代が5万円なのに対して、修理費が80万円かかるとします。この場合、時価額50万円+買替諸費用5万円−スクラップ代5万円です。そのため、修理額の方が高いことから、経済的全損となり、保険会社から支払われるのは50万円になります。
2. 修理額が経済的全損の場合の額を上回るとの立証責任は「加害者側」にある。
まず、被害者側は修理にかかる費用を、修理工場の見積書などで証明します。これに対し、加害者側(保険会社)が「修理費は車の時価額を上回っている(=経済的全損だ)」と主張して賠償額を制限したいのであれば、 修理額が経済的全損の場合の額を上回るとの立証責任は「加害者側」にあります。
つまり、「修理するには80万円かかります」という被害者の主張に対し、加害者側が「いや、その車の価値は50万円しかないので、50万円までしか払いません」と反論するためには、「なぜ50万円だと言えるのか」という客観的な根拠を、加害者側が示さなければならないのです。
もし相手の保険会社から「経済的全損なので時価額までしか支払えません」と言われたら、被害者としては立証責任があるわけではないものの積極的に「その時価額の根拠となる客観的な資料(レッドブックの写しや、中古車市場のデータなど)を提示」し、相手の主張に理由がないことを反論していきましょう。
3. 車の価値(時価額)はどうやって調べる?
車の時価額を調べるには、客観的で公平な方法が用いられます。主に以下の3つの方法があります。
① レッドブック(自動車価格月報)
中古車業界で広く利用されている、車種・年式・型式ごとの中古車価格の参考書です。保険会社や裁判所でも非常に重視される資料で、最も客観性が高いとされています。ただし、古い型式の自動車などは掲載されていないといった問題があります。
② インターネットの中古車市場価格
Goo-netやカーセンサーといった中古車情報サイトで、自分の車と「同一の車種・年式・型式・グレード・色・走行距離」の車が、市場でいくらで販売されているかを調べる方法です。 この場合、1台だけでなく、複数の同等条件の車両をリストアップし、その平均価格を算出することで、客観的な市場価格として主張することができます。これは個人でも行える、非常に有効な立証方法です。
裁判例でも、インターネットの中古車市場価格を元に、車の時価額を算定しているものが複数あります。
③ 定率法(減価償却)による計算
年式が古く(目安として登録から10年以上)、中古車市場にも同等の車がほとんど出回っていないような場合は、上記の方法で時価額を算定するのが難しくなります。
そのようなケースで例外的に用いられるのが、「新車価格の10%」を一律で時価額とする考え方です。これは、車の耐用年数を考慮した減価償却の考え方で、「どんなに古い車でも、部品としての価値などが残っているため、最低でも新車価格の10%程度の価値はあるだろう」という裁判などにおける実務的な扱いです。
あくまで他の方法で時価額を算定できない場合の最終手段ですが、古い車の場合はこの基準で交渉が行われることも少なくありません。実際に、加害者側は、この③で計算する場合が最も低い金額になる傾向があるため、この金額で提示してくることがあります。
まとめ:泣き寝入りせず、正当な賠償額を得るために
物損事故の賠償交渉は、専門知識が絡むため、交渉のプロである相手方保険会社のペースで話が進んでしまいがちです。保険会社が提示する「時価額」が、必ずしも適正とは限りません。
ここで泣き寝入りせず、あなたの愛車の正当な価値を主張するために、弁護士に依頼するという選択肢が極めて有効です。 弁護士は、あなたの代理人として次のような活動を行います。
- 相手方の提示する時価額が、レッドブックや市場価格といった客観的資料に基づいた適正なものか、専門的な観点から厳しくチェックします。
- 加害者側にある「立証責任」を根拠に、不当に低い時価額の主張を退け、より高額な賠償額を目指した交渉が可能です。
- 車両本体の価格だけでなく、買替諸費用など、請求できる可能性のある損害を漏れなく請求します。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用負担なく弁護士に依頼できます。
保険会社の提示額に少しでも疑問を感じたら、すぐに諦めてしまうのではなく、一度専門家である弁護士に相談してみることを強くお勧めします。