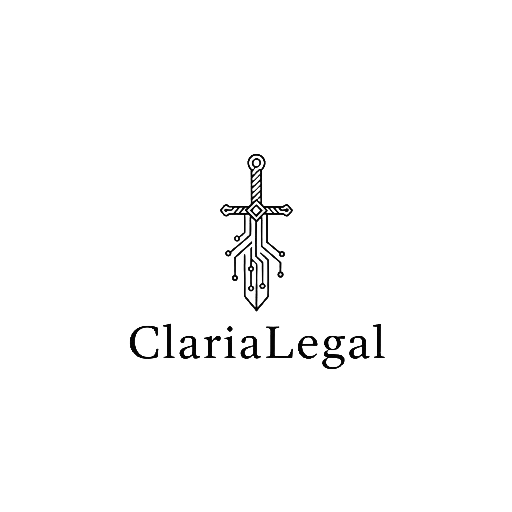遺言書で「特定の相続人に全財産を譲る」とした場合でも、他の相続人の最低限の権利である「遺留分」を無視することはできません。特に近年の法改正により、実務の運用が大きく変わっています。気をつけるべき重要ポイントは以下の4点です。
- 【金銭解決の原則】「不動産の一部」ではなく「現金」を用意できるか?
かつては遺留分を請求されると、不動産などの「現物」が共有状態になってしまうことがありましたが、2019年の民法改正によりルールが一変しました。
ポイント: 現在の「遺留分侵害額請求」は、全額「金銭(現金)」で支払う債権となります。
リスク: 不動産などの資産はもらったが、手元に現金がない場合でも、請求されたら現金を払わなければなりません。 最悪の場合、「遺留分を払うために、せっかく相続した不動産を売り払わなければならない」という本末転倒な事態に陥ります。
対策: 遺産を受け取る側(受遺者)に、遺留分を支払えるだけの「流動資産(現金)」があるか、あるいは生命保険金などを活用して納税資金・遺留分対策資金を準備できているかが鍵となります。
- 【時効の壁】「1年」という短い期限を知っているか?
遺留分の権利は、いつまでも主張できるわけではありません。非常に短いタイムリミット(消滅時効)が設定されています。
ポイント: 遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺言があったことを知った時から1年間」行使しないと時効で消滅します(除斥期間は相続開始から10年)。
リスク:
請求する側: 悠長に話し合いをしている間に1年が経過すると、権利が消滅して一円ももらえなくなります。まずは内容証明郵便で意思表示をして「時効を止める」必要があります。
請求される側: 相手が権利を知ってから1年以上経過していれば、「時効だ」と主張して支払いを拒絶できる可能性があります。いつ相手が遺言の内容を知ったか、その証拠が重要になります。
- 【計算の遡及】「過去の贈与」も計算に含まれる(10年ルール)
遺留分の大元となる基礎財産(遺産総額)は、亡くなった時に残っていた財産だけではありません。生前に行われた贈与も「持ち戻し」計算されます。
ポイント: 相続人に対する生前贈与は、「相続開始前10年間」のものが遺留分算定の基礎財産に含まれます(第三者への贈与は原則1年前まで)。
リスク: 「財産はもう生前に渡してあるから、遺産はゼロだ」と思っていても、その贈与が10年以内であれば、その分も計算に組み込まれます。 逆に言えば、「特定の相続人に財産を集中させたいなら、10年以上かけて計画的に生前贈与を行う」ことで、遺留分対策としての効果を確定させることができます。
- 【計算の落とし穴】「基礎財産」と「実際の遺留分として請求できる額」の算定で異なる「持ち戻し」のルール
遺留分の計算は非常に複雑ですが、最も誤解されやすく、かつ争点になるのが「過去の贈与をどこまで計算に入れるか(持ち戻し)」という点です。実は、計算のフェーズによって「10年の壁」がある場合とない場合があります。
ポイント:計算は「2段階」で考える 遺留分の計算は、大きく分けて(A)「全体の財産額の決定(基礎財産)」と、(B)「個別の侵害額の決定」の2段階で行われます。
(A) 基礎財産の計算(請求の「枠」を決める時):【10年以内の制限あり】 「遺留分全体がいくらになるか」を計算するための財産総額には、相続人に対する生前贈与は「原則として相続開始前の10年間」のものしか含まれません。
(例:20年前に貰った贈与は、原則として遺留分計算の土台(分母)には含まれません。)
(B) 具体的侵害額の計算(実際に払う額を決める時):【期間制限なし(無制限)】 ここが盲点です。実際に請求できる額(侵害額)を算出する際、「請求者自身が生前に受け取っていた利益(特別受益)」を差し引く必要があります。 実務上の解釈として、この「請求者自身が過去に貰っていた分」の控除については、10年という期間制限に関わらず、過去のすべての贈与が持ち戻し(差し引き)の対象となると考えられています。
リスクと対策:
もし請求者自身が「10年以上前」に結婚資金や住宅資金などで多額の援助を受けていた場合であっても、請求者は10年以上前なのだから持ち戻しの対象ではないとして勘違いし、「それは昔のことだから関係ない」と主張するかもしれません。
しかし、遺留分侵害額請求を受ける側は、「請求者が過去(20年前)に貰った分は、今の請求額から差し引かれるべきだ(期間制限はない)」と主張されることになります。
結果として、計算上は「請求者の遺留分侵害額はゼロ(または大幅減額)」となるケースも多々あります。
まとめ(4点を含めた全体像)
金銭解決の原則: 現金がないと不動産を売る羽目になる。
時効の壁: 請求は相続の開始及び遺留分侵害の事実を知ってから1年以内にしないと消滅する。
遡及計算(相手方): 財産を隠そうとしても直近10年の贈与は暴かれる。
計算の非対称性(自分側): 請求者が過去に受け取った利益は、10年以上前のものであっても徹底的に差し引く(持ち戻す)ことで、請求額を圧縮できる。
遺留分争いにおいては、単に「遺産の何分の1」という計算ではなく、「過去数十年分の歴史(誰がいつ何をもらったか)」を期間制限のルールを使い分けながら精査することが、最大の防御策となります。