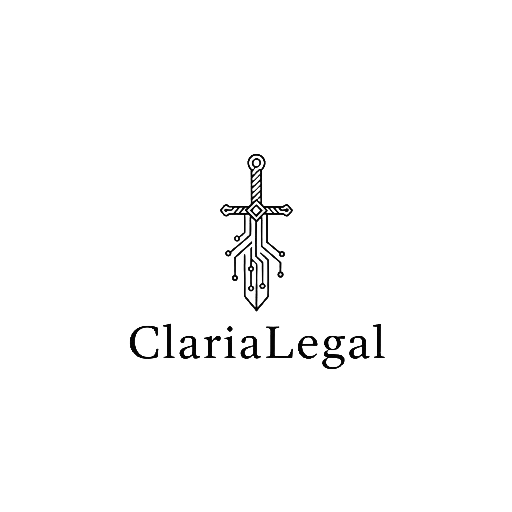【解説】離婚後の子育てルールが変わる!2024年民法改正の重要ポイント
2024年5月に成立した改正民法により、離婚後の子の養育に関するルールが大きく見直されることになりました。この改正は、父母が離婚した後も子の利益を第一に考え、共に養育責任を果たしていく社会を目指すものです。
この記事では、法務省が公開した資料をもとに、主な変更点を分かりやすく解説します。この法律は2026年5月までに施行される予定です 。
ポイント1:離婚後も「共同親権」が選択可能に
これまで、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」しか認められていませんでした 。今回の改正で最も注目されるのが、**父母双方を親権者とする「共同親権」**が選択できるようになる点です 。
- 定め方:まずは父母の協議によって、共同親権にするか単独親権にするかを決めます 。協議がまとまらない場合や裁判離婚では、家庭裁判所が子の利益を最優先に考慮して決定します 。
- 単独親権となる場合:ただし、虐待やDVのおそれがある場合など、父母が共同で親権を行うことが困難だと認められる場合には、家庭裁判所は必ず単独親権と定めます 。
ポイント2:養育費の支払いを確保する新制度
養育費の不払いを解消するため、支払いを確保するためのルールが強化されます 。
- 法定養育費の新設:離婚時に養育費の取り決めがなくても、子を監護する親はもう一方の親に対し、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります 。これは暫定的なもので、最終的には父母の収入に応じた適正額を取り決めることが重要です 。
- 差押え手続きの簡易化:養育費の支払いが滞った場合、これまでは公正証書などがなければ財産の差押えが困難でした 。改正後は、父母間で作成した文書に基づいて差押えを申し立てることができるようになります 。
ポイント3:安全・安心な「親子交流」の実現へ
離婚後も親子が適切な形で交流を続けることは、子の成長にとって重要です。今回の改正では、安全・安心な親子交流を実現するためのルールが整備されました 。
- 試行的実施制度:家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試験的に行い、その状況を見ながら最適な交流の形を探る「試行的実施」の制度が設けられます 。
- 祖父母などとの交流:子の利益のため特に必要があると家庭裁判所が認める場合には、祖父母などの親族と子の交流について定めることができるようになります 。
ポイント4:財産分与の請求期間が5年に延長
離婚時の財産分与について、請求できる期間が離婚後
2年から5年に延長されます 。これにより、離婚後すぐに請求手続きを取ることが難しい場合でも、余裕をもって対応できるようになります。
また、財産分与を判断する際に考慮すべき事情(婚姻期間、各自の寄与の程度など)が法律上明記され、より公平な解決が図られるようになります 。
今回の法改正は、離婚後の家族のあり方に大きな影響を与えるものです。特に共同親権の導入や養育費の新制度は、多くの当事者にとって重要な変更点となります。ご自身の状況に合わせて、専門家への相談もご検討ください。