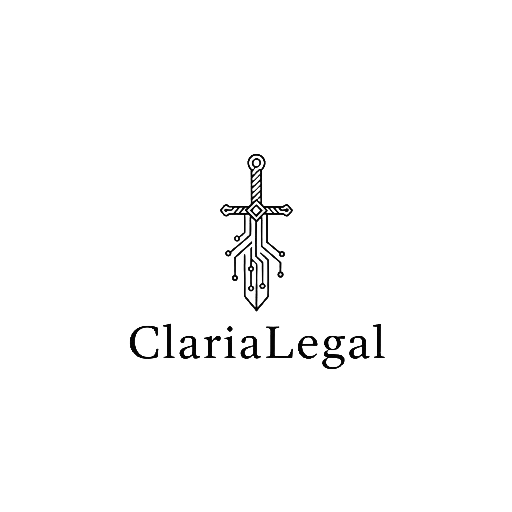刑事弁護、告訴・告発
逮捕されるかどうかはどのようにして決まるのか
在宅になるのか、逮捕されるのか。その区別はどのようになされるのかご説明します。
逮捕状が請求されて後日逮捕されるケースでは、主に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)」と「逮捕の必要性」という2つの法的要件によって決まります。
1. 逮捕の理由(犯罪の嫌疑)
まず、被疑者が特定の罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由」があるかどうかが審査されます。
- 物的証拠
- 目撃供述
- 防犯カメラ
- 犯行の自供
- 指紋・DNA・遺留品
- 犯行の動機がある
- 犯行可能性がある
2. 逮捕の必要性
嫌疑があっても、強制的に身柄を拘束する「必要性」がなければ逮捕状は発付されません。裁判官は、以下の事情を総合的に考慮して判断します。
- 逃亡のおそれ: 被疑者の年齢、境遇、定まった住居の有無、家族関係、職業などが考慮されます。
- 例えば、安定した仕事があり家族と同居している場合は、逃亡のおそれが低いと判断されやすくなります。
- 罪証隠滅のおそれ: 証拠を隠滅したり、関係者に口裏合わせを働きかけたりする現実的な危険性があるかどうかが検討されます。
- 客観的な証拠がすでに押収されている、被害者や目撃者と会うことが不可能に近い、被疑者が事実を認めている場合などは、隠滅のおそれが低いと判断される可能性が高まります。
3. 軽微な事件における制限(逮捕の制限)
法定刑が非常に軽い罪(30万円以下の罰金、拘留、科料)については、逮捕の要件がより厳格になります。以下のいずれかの場合に限り、逮捕が可能となります。
- 被疑者が定まった住居を有しない場合。
- 正当な理由がなく、出頭の求めに応じない場合。
4. 弁護活動による「逮捕・勾留」の回避
逮捕される可能性、あるいは逮捕後に引き続き拘束される(勾留)可能性を左右する要素として、弁護人による働きかけがあります。
- 早期の示談: 被害者との示談が成立している、あるいはその見込みがあることは「勾留の必要性」を低下させる重要な要素となります。
- 身元引受人の確保: 家族や勤務先の代表者が、釈放後の監督を誓約し、身元引受書を提出することで、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを説得的に主張できます。
- 任意捜査への協力: 正当な理由なく出頭を拒否せず、任意の取調べに応じている事績も、逮捕の必要性を否定する事情となります。
まとめると、逮捕される可能性は、「証拠に基づく犯罪の疑いの強さ」に加え、「住居の安定性や家族・職場の監督体制」、そして「捜査への協力姿勢や示談の状況」といった複数の要素を、裁判官が法的基準(理由と必要性)に照らして判断することで決まります。
逮捕後の流れはどうなのか
逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまでの身柄拘束期間は、最大で23日間に及ぶ可能性があり、この期間は「時間との戦い」と言われるほど迅速な対応が求められます。
1. 逮捕から検察官送致まで(最大48時間)
警察によって逮捕されると、警察官は被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致する手続(送致)をとらなければなりません。
- 警察での取調べ: 逮捕直後、警察官による「弁解録取」が行われ、事実を認めるかどうかが確認されます。
- 弁護人の活動: この段階での弁護人の最も重要な役割は、「初回接見」です。逮捕直後の被疑者は、今後の見通しが立たず不安な状態にあり、取調官の説得に屈して事実と異なる供述をするリスクがあります。弁護人は一刻も早く接見し、黙秘権や供述調書への署名押印拒否権について適切な助言を行います。
2. 検察官の勾留請求まで(最大24時間)
検察官は、警察から送致された被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕から合計72時間以内に、裁判官に対して「勾留(こうりゅう)」を請求するか、釈放するかを決めなければなりません。
- 勾留請求の要件: 検察官が「勾留が必要」と判断するのは、犯罪の立証ができていること及び犯人性がひとまず認められることを前提に、主に「定まった住居がない」「証拠隠滅の恐れがある」「逃亡の恐れがある」のいずれかの事由がある場合です。
- 弁護人の活動: 弁護人は、検察官が勾留請求を行う前に、勾留の要件がないことを主張する「意見書」を提出し、釈放を促します。
3. 裁判官による勾留の裁判
検察官が勾留を請求すると、裁判官が被疑者と面談する「勾留質問」が行われます,。
- 勾留決定: 裁判官が勾留の理由と必要性を認めた場合、勾留が決定します。
- 勾留請求却下: 裁判官が勾留を認めなかった場合、被疑者は釈放されますが、検察官が不服を申し立て(準抗告)、それが認められるまでは釈放されないこともあります。
4. 勾留期間(最大20日間)
勾留が決まると、原則として10日間身柄が拘束されます。
- 勾留の延長: 10日間で捜査が終わらない「やむを得ない事由」がある場合、検察官の請求により最大でさらに10日間延長されることがあります。
- 弁護人の活動: 勾留決定に対し不服がある場合は「準抗告」を申し立て、決定の取り消しを求めます。また、余罪の捜査を理由とした安易な勾留延長に対しても準抗告などで抗戦します。
5. 起訴・不起訴の判断
勾留期間の満了までに、検察官は被疑者を裁判にかけるかどうかを判断します。
- 起訴(公判請求): 刑事裁判が請求されます。身柄拘束は「被告人勾留」として継続しますが、この段階から「保釈」の請求が可能になります。
- 略式命令請求: 比較的軽微な事件で、公開の裁判を行わずに罰金刑を求める手続です。罰金を納付すれば釈放されます。もっとも証拠が弱く争えば不起訴になることもあり得る事件があるので、略式起訴に同意するか否かは個別具体的な判断が必要です。
- 不起訴処分: 嫌疑が不十分な場合や、情状により訴追の必要がないと判断された場合(起訴猶予)などは不起訴となり、即日釈放されます。
まとめ:各段階の制限時間
| 段階 | 制限時間 | 通算最大時間 |
|---|---|---|
| 逮捕から送致 | 48時間以内 | 48時間 |
| 送致から勾留請求 | 24時間以内 | 72時間 |
| 勾留(初回) | 10日間 | 13日間程度 |
| 勾留延長 | 最大10日間 | 計23日間程度 |
逮捕された後の早期釈放を実現するためには、勾留が決定される前の「逮捕から72時間以内」の弁護活動が極めて重要となります。この間に家族の身元引受書や示談の経過報告など、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す資料を揃えることが、その後の運命を大きく左右します。
警察での取調べに対してどのよう臨んだら良いのか
警察の取り調べ(取調べ)において、被疑者が自分自身の権利を守り、不当な不利益を被らないために注意すべきポイントは多岐にわたります。
1. 黙秘権(供述拒否権)の適切な行使
取調べにおいて、自分の意思に反して供述を強要されることはありません。これは憲法および刑事訴訟法で保障された黙秘権(供述拒否権)によるものです。
- 「話さないこと」による不利益はない: 捜査官から「黙秘を続けると反省していないとみなされ、罪が重くなる」などと言われることがありますが、裁判所が黙秘したこと自体を理由に量刑を重くすることは許されません。
- 雑談にも応じない: 核心部分だけでなく、氏名や身上経歴、あるいは取調官との「雑談」に対しても黙秘権は行使可能です。取調官は雑談を通じて情報を得ようとしたり、心理的な壁を崩そうとしたりするため、徹底して黙秘する場合は、取調室への移動中も含め一切の雑談に応じない姿勢が求められます。
- 助言の仕方のシミュレーション: 黙秘すると決めた場合、取調官から「なぜ黙秘するのか」と問われることがあります。その際は「弁護士の指示です」と答えたり、あるいは一切口を開かず沈黙を貫くなどの具体的な対応方法を、事前に弁護人と打ち合わせておくことが重要です。
- 場合によっては話すことも:初期の呼び出しや取調べ時には証拠の固さが不明確なので黙秘せざるを得ないものの、その後の警察の取り調べなどで証拠が固いことがわかる場合があります。この場合には黙秘せずに自供して被害者と示談した方が不起訴になる可能性が高まることもあるので、柔軟に対応する必要があります。弁護士との協議が必要な場面です。
2. 供述調書への署名押印拒否権の行使
取調べで話をした内容が書面にまとめられたものが「供述調書」ですが、これに対する署名・押印は慎重に行う必要があります。
- 署名押印の義務はない: 刑事訴訟法198条5項により、内容に誤りがないことを確認した後であっても、署名押印を拒絶することができます。
- 「作文」の危険性: 供述調書は被疑者の言葉がそのまま記録されるのではなく、取調官の主観や意図によって「作文」されることが一般的です。一度署名押印してしまうと、後の裁判でその内容を覆すことは極めて困難になります。
- 証拠としてのリスク: 否認事件において、一部でも自白に近いニュアンスが含まれた調書を作成されると、それが決定的な有罪証拠となるリスクがあります。そのため、弁護人は「供述はしても調書には署名しない」という戦略を助言することもあります。
3. 被疑者ノートによる取調べ状況の記録
取調べの状況を被疑者自身が詳細に記録しておくことは、防御活動において極めて有効です。
- 日々の記録: 取調べの時間、取調官の発言(脅迫や利益誘導の有無)、供述調書の作成状況などを、毎日「被疑者ノート」に記録します。
- 違法捜査の証拠化: 捜査官が「認めれば不起訴にする」といった不適切な利益誘導を行ったり、弁護人を誹謗する発言をしたりした場合、その記録は供述調書の任意性を争う際の重要な資料となります。また、記録すること自体が捜査官に対する牽制にもなります。
4. 不当・違法な取調べへの対処
捜査官が威圧的な態度をとったり、不適切な言葉を投げかけたりした場合、弁護人を通じて即座に抗議を行う必要があります。
- 弁護士との信頼関係破壊の阻止: 捜査官が「あの弁護士は金目当てだ」「解任したほうがいい」などと発言することは、弁護人依頼権を侵害する不当な行為です。このような発言があった場合、弁護人は抗議文を提出したり、監督官に苦情を申し立てたりします。
- 検察庁・警察に対する苦情申出: 違法な取調べに対しては、警察の「取調適正化指針」や検察庁の通達に基づき、正式な苦情申出書を提出して是正を求めることが可能です。
5. 取調べの可視化(録音・録画)の活用
取調べプロセスの透明性を高めるため、全過程の録音・録画を求めることができます。
- 全過程の録音・録画を申し入れる: 一部の都合の良い場面だけが録画されることを防ぐため、弁護人は「取調べ全過程」の録音・録画を検察・警察に申し入れます。
- 拒否された場合の意味: 捜査機関が録音・録画の申入れを拒否して作成された自白調書については、後の裁判でその任意性や信用性を争う際の有力な事情となります。
まとめ
警察の取り調べにおいて最も重要なのは、「孤独な密室で捜査官のペースに呑まれないこと」です。そのためには、事前に弁護人と密に接見し、黙秘権や署名押印拒否権の行使方法を具体的にシミュレートし、何かあればすぐに弁護人に相談するという姿勢を貫くことが不可欠です。
不起訴を得るためにすべきこと
不起訴処分を得るための示談交渉において、弁護人が留意すべき具体的なポイントを資料に基づき整理します。示談は検察官が起訴・不起訴を判断する際の最も重要な考慮要素の一つです。
1. 示談交渉に向けた事前の準備
交渉を開始する前に、被疑者本人と方針を十分に協議することが不可欠です。
- 被疑者の意思確認と謝罪の意向: 被疑者本人が事実を認め、真摯に反謝しているかを確認します。被疑者の了解なしに示談を進めることはできません。
- 賠償条件の決定: 提示する賠償金の金額(実損額、慰謝料、迷惑料)や、告訴の取消しを条件とするかなどをあらかじめ決めておきます。
- 被害者の連絡先の入手: 検察官を通じて被害者の連絡先(氏名・電話番号等)の開示を求めます。被害者が拒否した場合は、弁護人の連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
2. 被害者へのアプローチと面談の要領
被害者の感情に配慮し、誠実な態度で接することが重要です。
- 最初の接触: 電話での連絡が一般的ですが、唐突な連絡を避けるため、事前に弁護人から手紙(初動の挨拶と謝罪の意向を伝えるもの)を出すことが丁寧な手法です。
- 「示談ありき」を避ける: 最初から「示談したい」と切り出すのではなく、被害者の心情に耳を傾け、反省の意を伝える姿勢を貫きます。被害者からの「本当に反省しているのか」「再犯の恐れはないか」といった問いに誠実に答えられるよう、事前に被疑者と打ち合わせておきます。
3. 不起訴に直結する示談書の作成ポイント
示談書には、単なる金銭解決だけでなく、検察官の判断に影響を与える以下の文言を盛り込むことがポイントです。
- 宥恕(ゆうじょ)文言: 被害者が被疑者を「許す」、あるいは「刑事処罰を望まない」という意思表示を含めます。
- 告訴の取消し・被害届の取下げ: 親告罪の場合は「告訴を取り消す」旨を明記し、別途「告訴取消書」も作成して署名捺印をもらいます。
- 清算条項: 今後、本件に関し民事上の請求を互いに行わないことを確認します。
- 内容の正確な説明: 調印の際、被害者が後で「内容を理解していなかった」と検察官に説明することがないよう、条項の意味を丁寧に解説し、納得の上で署名をもらいます。
4. 示談成立後の迅速な対応
- 検察官への報告: 示談書や告訴取消書の原本(または写し)を直ちに担当検察官に提出します。
- タイムリミットの意識: 勾留されている事件では、勾留期間(通常10〜20日間)が満了するまでに示談を成立させ、検察官に提出しなければなりません。
5. 示談が成立しない場合の対応
被害者の処罰感情が強く示談が困難な場合でも、以下の努力を証拠化して検察官に伝えます。
- 謝罪文の提出: 被疑者本人の反省文や謝罪文を弁護人を通じて渡そうと試みます。
- 被害弁償の提供・供託: 金銭の受領を拒否された場合、弁護士会での預かり金や法務局への供託、あるいは贖罪寄付を行ったことを報告書にまとめ、被害回復の努力を尽くしたことを伝えます。
これらの活動を通じて、検察官に「訴追の必要性がない(起訴猶予)」あるいは「訴訟条件を欠く」と判断させることが、不起訴処分獲得への鍵となります。
供託や贖罪寄付は有効なのか
被害者が示談を拒否した場合でも、「供託」や「贖罪(しょくざい)寄付」を行うことは、被告人・被疑者の反省や被害回復への努力を示す事実として、処分を軽くする上で一定の有効性を持ちます。
1. 供託(きょうたく)の有効性と意義
被害者が賠償金の受け取りを拒否している場合、法務局に対して賠償金相当額を預ける「供託」という手続をとることができます。
- 被害回復の努力の証明: 供託を行うことで、加害者に民事上の損害賠償債務を履行する意思があることや、客観的に被害弁償の準備ができていることを検察官や裁判所に証明できます,。
- 供託の要件: 原則として、被害者に対して実際に金銭の提供(弁償の申し出)を行い、それを拒絶されたことが要件となります。
- 処分の判断材料: 供託証明書を意見書に添付して提出することで、示談が成立していない事案であっても、「被害回復の努力を尽くした」という有利な情状として考慮され、不起訴処分(起訴猶予)や減刑につながる可能性があります。
2. 贖罪寄付(しょくざいきふ)の有効性と意義
被害者への直接の支払いが困難な場合、弁護士会や公益団体などに対して寄付を行う「贖罪寄付」という手法もあります。
- 社会的な謝罪の意向: 被害者が受領を拒否している場合や、薬物事犯のように特定の被害者がいない事件において、自らの罪を償う(社会的な被害回復を行う)姿勢を示すために行われます。
- 証明書の活用: 寄付を行うと「贖罪寄付付証明書」が発行され、これを証拠として提出することで、被告人の反省の情を補強する材料となります。
- 限定的な効果: ただし、特定の被害者が存在する事件においては、被害者の処罰感情が残っている以上、贖罪寄付を実施しても示談成立ほどの有利な効果は得られないと判断される場合もあります。
3. 示談が成立しない場合のその他の対応
資料では、供託や寄付以外にも、誠意を示すための以下の活動が挙げられています。
- 弁護人による預かり: 被害者側の感情が極めて強く、現時点では一切の接触や供託すら拒まれるような場合、弁護人が賠償金を預かり、いつでも支払える状態にあることを報告書で伝える方法があります。
- 謝罪文の提出: 被害者側が金銭の受領を拒否しても、弁護人を通じて真摯な謝罪文を渡そうと試み、その経過を記録化しておくことが重要です。
- 示談経過報告書の提出: 示談が成立しなかったとしても、「示談を申し入れた事実」や「示談に至らなかった相当な理由(被害者側の過大な要求や頑なに拒否するなど)」を詳細な報告書(示談経過報告書)にまとめて提出することで、検察官の判断に好影響を与えることが可能です。
4. 処分の決定における重み
- 不起訴の可能性: 資料によれば、示談が成立しなければ不起訴処分は得られないと考えがちですが、示談に代えてとった措置(供託など)を疎明することで、不起訴処分を獲得できることは可能とされています。
- 裁判での量刑: すでに起訴されている場合でも、被害回復の努力を尽くしたプロセス自体が、執行猶予の獲得や減刑に向けた重要な情状として裁判所に考慮されます。
まとめると、被害者に拒否された場合でも、供託や贖罪寄付は「できる限りの被害回復への真摯な努力」として法的に評価されるため、非常に有効な弁護活動となります。
保釈はどのようにして認められるのか
刑事事件における保釈(ほしゃく)とは、起訴された後に、保証金の納付を条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度です。保釈が認められるかどうかは、法律で定められた要件(権利保釈・裁量保釈など)に基づき、裁判所(第1回公判前は裁判官)が判断します。
以下に、保釈がどのようにして決まるのか、その仕組みと判断基準、手続の流れについて詳しく解説します。
1. 保釈の種類と判断基準
裁判所は、主に以下の「権利保釈」と「裁量保釈」の観点から判断を行います。
① 権利保釈(原則として認められるべき保釈)
刑事訴訟法89条に定められた除外事由(不許可事由)に該当しない限り、裁判所は保釈を許さなければなりません。主な除外事由は以下のとおりです。
- 重大な罪: 死刑、無期、または長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき。
- 前科: 過去に重大な罪(懲役・禁錮10年超)で有罪判決を受けたことがあるとき。
- 常習性: 常習として罪を犯したとき。
- 罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ: 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。実務上、この「罪証隠滅のおそれ」が最も頻繁に問題となります。
- 証人威迫のおそれ: 被害者に危害を加えたり、証人を脅したりするおそれがあるとき。
- 住居不定: 被告人の住居が分からないとき。
② 裁量保釈(裁判所の判断で認められる保釈)
権利保釈の除外事由(例えば罪証隠滅のおそれなど)に該当する場合であっても、裁判所が「適当と認めるとき」には、職権で保釈を許すことができます(刑事訴訟法90条)。 この判断に際しては、被告人の健康状態、経済状況、家族環境、社会生活上の不利益、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度などが総合的に比較考量されます。
2. 保釈決定までの具体的な流れ
保釈は、弁護人などからの「保釈請求」をきっかけとして、以下のプロセスを経て決定されます。
- 保釈請求: 弁護人、被告人、または一定の親族等が裁判所に請求書を提出します。
- 検察官の意見聴取: 裁判所は、保釈の許否について検察官に意見を求めます(求意見)。検察官は通常、保釈に反対する「不相当」という意見を出すことが多いです。
- 裁判官との面接: 弁護人は、検察官の意見を確認した上で、裁判官と面接(面接交渉)を行い、保釈を認めるべき具体的な事情を直接訴えます。
- 保釈許可・却下の決定: 裁判所が最終的な判断を下します。許可される場合は、同時に「保釈保証金」の金額が指定されます。
3. 保釈保証金(保釈金)の決まり方
保釈を許可する際、裁判所は被告人の出頭を保証するのに足りる相当な金額を定めます(刑事訴訟法93条)。
- 金額の目安: 一般的には150万円から300万円程度となることが多いですが、罪の重さ、被告人の資産状況、前科の有無、事件の重大性などによって大きく変動します。
- 考慮要素: 被告人が「逃亡すると没収されて困る」と感じるだけの心理的・経済的制約となる金額が設定されます。
4. 保釈の条件(指定条件)
保釈が認められる際には、単に金を払うだけでなく、以下のような指定条件を守ることが義務付けられます。
- 住居の制限: 指定された住所(自宅など)に住まなければならず、旅行や転居には裁判所の許可が必要です。
- 接触の禁止: 事件の被害者や共犯者、関係者と連絡を取ったり会ったりすることが禁止されます。
- 裁判への出頭: 裁判所から召喚を受けたときは、必ず指定された日時に出頭しなければなりません。
これらの条件に違反したり、正当な理由なく裁判に出頭しなかったりした場合、保釈は取り消され、保証金が没取されることになります。
まとめると、保釈は「罪証隠滅や逃亡の恐れ」の有無を主軸としつつ、被告人の健康や家族関係などの社会的事情を総合的に判断して、裁判官が最終的な許否と金額を決定します。
保釈に必要なお金はいくらなのか
刑事手続きにおける保釈保証金(保釈金)の金額は、一律に決まっているわけではなく、裁判官が個別の事案ごとに判断して決定します。提供された資料に基づき、その決定基準や相場、金額に影響を与える要因について詳細に解説します。
1. 保釈保証金額の決定基準
裁判所が保釈保証金の額を定める際には、刑事訴訟法第93条2項に基づき、以下の要素が考慮されます。
- 犯罪の性質および情状: 罪名、罪質、法定刑、犯行の動機、態様、手段、計画性、組織性、被害結果などが含まれます。
- 証拠の証明力: 有罪判決の蓋然性がどの程度あるかという点です。
- 被告人の性格および資産: 粗暴性や犯罪の常習性の有無、社会的地位(組織暴力関係者か否かなど)に加え、被告人個人の資産だけでなく、被告人の信用や保護者の資産・信用も含まれます。
- 被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額: 被告人が逃亡した場合に没取(没収)されるという心理的負担を与え、公判への出頭を確実にさせるのに十分かつ必要な金額である必要があります。
2. 一般的な相場
実務上の運用として、保釈保証金の相場については以下の傾向が示されています。
- 最低ラインと標準額: 現在の運用では、最低でも150万円、通常は200万円程度と言われています。
- 一般的な事案: 特別な事情がない限り、150万円前後になることが多いとされています。
- 資力が乏しい場合: 被告人の資力が極めて低い場合、裁判官との面談等を通じて交渉することで、150万円を下回る金額(例えば100万円程度など)が定められることもあります。
3. 金額が高額になる要因
事案によっては、相場を大きく上回る金額が設定されることがあります。
- 被告人の資産状況: 被告人が非常に裕福である場合、少額では逃亡抑止力にならないと判断され、ニュースで報じられるように1000万円を超えることもあります。
- 事件の重大性と前科: 重大事件や同種前科がある場合、実刑判決の可能性が高まるため、逃亡を防止するために保証金額も引き上げられる傾向にあります。
- 別件での勾留: 複数の事件で逮捕・起訴され、個別の裁判所に係属している場合、勾留事実ごとに保釈決定が必要となるため、総額では高額になることがあります。
4. 再保釈(一審判決後)の場合
第一審で実刑判決を言い渡された後、控訴して再度保釈を請求する「再保釈」の場合、保証金額は増額されるのが一般的です。
- 増額の目安: 第一審の保釈時の1.5倍程度とされることが多く、具体的には50万円から100万円程度増額され、総額で300万円や400万円といった、きりのよい数字で設定される例が多いとされています。
5. 保釈金の準備が困難な場合の対応
多額の現金を即座に用意できない場合、以下の制度の利用が検討されます。
- 日本保釈支援協会: 保釈保証金の立替え事業を行っている機関です。
- 保釈保証書による代用: 弁護士協同組合連合会などが発行する「保釈保証書」を、現金の代わりに裁判所に差し出すことで保釈を許可してもらう手続です(刑事訴訟法94条3項)。ただし、裁判所によっては一部を現金で納付するよう求められることもあります。
保釈保証金は、裁判が終了し、被告人が条件を守って出頭し続けていれば、無罪・有罪(実刑または執行猶予)にかかわらず、最終的には全額還付されます。
保釈保証金とは、起訴後の被告人の身柄拘束を解く「保釈」を許可する際に、裁判所へ預ける金銭のことです。
この制度は、被告人に保証金の没取という心理的・経済的な負担を課すことで、裁判への出廷を確保し、逃亡や罪証隠滅を防止することを目的としています,。以下に、その基準、相場、納付方法、返還の仕組みについて詳細に解説します。
1. 金額の決定基準と相場
裁判所が保釈保証金の額を決定する際は、法律(刑事訴訟法93条2項)に基づき、以下の要素が総合的に考慮されます,。
- 罪の性質および情状: 罪の重さや犯行態様、社会的影響など,。
- 証拠の証明力: 有罪判決の蓋然性の程度。
- 被告人の性格および資産: 粗暴性や再犯の可能性、経済状況(本人の資産だけでなく、家族の資産や信用も含まれる)。
実務上の相場: 一般的には150万円から300万円程度になることが多いとされています,,。ただし、資産家や重大事件の場合は1000万円を超えることもあれば、経済的に困窮している被告人の軽微な事件では150万円を下回る(例:100万円など)ケースもあります。
2. 納付方法と代用措置
保釈が許可されても、保証金が納付されなければ被告人は釈放されません。
- 現金納付: 裁判所の窓口へ現金で納付するのが原則です。近年では、インターネットバンキングやATMを利用した「電子納付(Pay-easy等)」も可能になっています。
- 保釈保証書による代用: 多額の現金を即座に準備できない場合、裁判所の許可を得て、日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会などが発行する「保釈保証書」をもって金銭の納付に代えることができます,,。
- 身元引受人の協力: 弁護人は被告人の親族や知人に働きかけ、保証金の準備や身元引受の協力を取り付けます。
3. 保釈条件と没取(没収)
保釈された被告人には、裁判所から指定条件が課されます,。
- 主な条件: 制限住居に居住すること、裁判所への出頭、逃亡・罪証隠滅の禁止、事件関係者との接触禁止などが挙げられます。
- 保証金の没取: 被告人が逃亡したり、正当な理由なく公判に出頭しなかったり、指定条件に違反した場合には、裁判所の決定により保証金の全部または一部が没取されることがあります。
4. 保証金の還付(返還)
保釈保証金は、あくまで「保証」のために預けているものであるため、裁判が終了すれば被告人に返還されます。
- 還付のタイミング: 有罪(執行猶予付を含む)、無罪、刑の免除などの判決が宣告されたときや、勾留が取り消されたときなどに還付手続が行われます。
- 返還までの期間: 判決宣告から概ね1週間程度で、指定した口座に振り込まれるのが一般的です。
- 実刑判決の場合: 実刑判決が出た場合でも、判決宣告時点ではまだ「確定」していないため、その場で保証金が返還されるわけではありません。再保釈を請求する場合、前の保証金をそのまま流用したり、不足分を積み増したりして手続を進めることになります。
まとめると、保釈保証金は被告人の自由と裁判の円滑な進行を天秤にかけるための重要なツールであり、その金額や条件は個別の事案ごとに慎重に調整されます。
警察による携帯電話の捜査はどのような流れなのか
警察によるスマートフォンやパーソナルコンピュータ(PC)の証拠収集は、近年の刑事訴訟法改正(平成23年改正、24年施行)により、デバイス本体の差し押さえだけでなく、ネットワーク上のデータや通信履歴まで広範囲に及んでいます。
提供された資料(『令状事務処理の手引』『令状実務詳解』等)に基づき、具体的にどのような証拠収集が可能なのか、その範囲と手法を解説します。
1. 端末本体および内部データの差し押さえ
警察は、裁判官の発付する令状(捜索差押許可状)に基づき、スマートフォンやPCなどの「電磁的記録媒体」を差し押さえることができます。
- デバイス本体の収容: 証拠が含まれる可能性のあるスマホやPC、USBメモリ、外付けハードディスクなどの機器そのものを持ち去ることが可能です。
- データの複写・印刷: 差し押さえるべき対象が電磁的記録である場合、機器を移動させるのではなく、必要なデータだけを他の記録媒体(CD-Rなど)に複写したり、書面に印刷したりして差し押さえる手法も認められています。これは、業務への支障を最小限に抑えるための配慮として行われることがあります。
2. リモートアクセスによる外部データの収集
平成23年の法改正により新設された「リモートアクセスによる複写」という手法により、差し押さえた端末とネットワークで接続された外部サーバー上のデータも収集の対象となります。
- クラウドやSNSのデータ: スマホやPCを操作して、その端末と電気通信回線で接続されている外部の記録媒体(クラウドストレージ、メールサーバー、社内用ファイルサーバーなど)に保存されているデータを、差し押さえた端末や警察のメディアに複写して差し押さえることができます。
- 対象範囲の特定: 令状には、複写すべき電磁的記録の範囲(例:特定のメーラーのアカウントでアクセス可能な領域、ブラウザの履歴にあるURLのアクセス領域など)を具体的に記載する必要があります。
- パスワード等の必要性: リモートアクセスのためには、原則として被疑者のIDやパスワードを把握している必要があります。差し押さえの現場でこれらを確認せずに、後から警察署等で独自にアクセスして複写することは許されないとされています。
- 国外サーバーへの対応: サーバーが日本国外にある場合、他国の主権侵害の問題が生じる可能性があるため、原則として捜査共助などの方法によるべきですが、利用者の同意がある場合などは許容されるという議論もあります。
3. プロバイダ等に対する記録命令付差押え
警察が直接端末を操作するのではなく、サービスプロバイダ等(通信事業者など)に対してデータを提出させる「記録命令付差押え」という制度もあります。
- データの作成・提出命令: 裁判官の令状に基づき、プロバイダ等に対してサーバー内に保管されている特定のデータ(電子メールの通信履歴、接続ログなど)をCD-R等に記録、または印刷させ、それを差し押さえる方法です。
- 活用例: 通信事業者が保管している接続ログや、メールサーバー内の特定の電子メールアドレスの送受信履歴などが対象となります。
4. 通信履歴や位置情報の取得
携帯電話会社などのキャリアが保有する情報の差し押さえも頻繁に行われます。
- 通話履歴: 特定の電話番号における一定期間の発着信履歴や料金明細内訳を、電磁的記録媒体として差し押さえることが可能です。
- 位置情報: 携帯電話が基地局との通信に用いた際の基地局に関する位置情報リストも、特定の期間を指定して差し押さえることができます。
5. 証拠収集における制限と注意点
警察によるデジタル証拠の収集には、憲法の令状主義に基づく一定の制約があります。
- 「必要な処分」としての強制力: 捜索差押許可状の執行にあたり、必要があるときは、警察は対象のスマホのロックを解除(錠をはずすのと同様の処置)したり、PCを操作したりするなどの「必要な処分」を行うことが認められています。
- パスコードを教えない場合:パスコードを教えない場合には解析することになりますが、iPhoneは解析できないことが多く解除できないことも多いのが実際です。
- 顔認証:身体検査令状と捜索差押許可状により、顔を強制的に押さえつけられて顔認証を解除されることになります。
- 関連性の要件: 差し押さえの対象は、令状に記載された被疑事実と関連性があるものに限られます。無関係なプライベートな写真を無差別に閲覧・収集することは、本来許されません。
- 証拠の特定性: デジタルデータは大量に含まれていることが多いため、捜査機関はできる限り対象物を特定して記載するように努めるべきであり、裁判所も「正当な理由」が認められる範囲に限定して許可を出します。
まとめると、警察はスマホやPC本体だけでなく、そこに繋がっているクラウド上のメールやデータ、SNSの投稿内容、さらにはキャリアが保管する通話・位置情報の履歴まで、裁判官の令状があれば非常に広範囲に証拠を収集することが可能です。ただし、これらを行うには被疑事実との関連性が厳格に求められ、特にリモートアクセスの場合は接続先やID等の特定が令状で要求されます。
警察による捜索差し押さえはどのような流れなのか
警察による捜索・差押えは、令状主義に基づき、原則として裁判官が発付する令状に従って厳格な手続のもとで実施されます。
1. 令状の請求と審査・発付(裁判所の手続)
捜索差押許可状の発付は、捜査機関(検察官、検察事務官、司法警察員)が裁判官に対して請求することから始まります。
- 相当な理由の疎明: 捜査機関は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由」があることを、捜査記録などの資料によって疎明しなければなりません。
- 対象の特定: 捜索すべき場所、身体、物、および差し押さえるべき物を具体的に特定する必要があります。例えば、マンションの一室を捜索する場合、その管理権が及ぶ範囲(専有部分)に限定されます。
- 事務的プロセス: 裁判所では、請求書の受付後、書記官が形式的な点検を行い、裁判官が実質的な審査を経て許可状に記名押印します。
2. 執行の着手と「必要な処分」
捜査機関が現場に到着し、捜索・差押えを開始する際の具体的な動きは以下の通りです。
- 令状の提示: 原則として、処分を受ける者に対して令状を提示しなければなりません。ただし、薬物事件などで証拠隠滅の蓋然性が極めて高い場合、実効性を確保するために、入室した直後に提示する「事後的提示」が例外的に認められることもあります。
- 「必要な処分」としての破壊活動: 刑事訴訟法111条に基づき、捜査官は捜索の目的を達成するために「錠をはずし、封を開き」といった必要な処分を行うことが認められています。相手方の同意が得られない場合や、鍵の提供を拒否された場合には、必要最小限度の範囲でドアを解錠したり、窓ガラスや金庫を破壊して執行することも適法とされます。
- 現場保存措置: 令状提示の前であっても、捜索場所に立ち入って現状を保存し、関係者による証拠の破壊や隠匿を制止する措置をとることが許容されています。
3. 捜索・差押えの実施と立会い
捜索の過程では、プライバシー保護と適正手続の確保のため、第三者の関与が求められます。
- 立会人の確保: 住居等で捜索を行う場合、住居主やその近親者、あるいは自治体の職員などの立会人を置かなければなりません。
- 捜索の範囲: 令状に記載された場所や物に限定されますが、捜索中に住居人が証拠物を着衣のポケットに隠した場合などは、その身体に対しても捜索が及ぶことがあります。
4. 差押えの完了と記録の交付
証拠物を確保した後には、以下の手続が行われます。
- 押収品目録の交付: 捜査官は、差し押さえた物の名称、数量、形状などを詳細に記載した「押収品目録」を作成し、処分を受けた者に交付しなければなりません。
- 捜索証明書の交付: 証拠物が発見されず捜索のみで終了した場合、希望すれば「捜索証明書」の交付を受けることができます。
5. 特殊な捜索・差押えの手法
現代の捜査では、物理的な場所以外の対象に対しても高度な手法が用いられます。
- 電磁的記録(デジタル証拠): パソコンを差し押さえる際、ネットワークで接続された外部サーバー上のデータを複写して差し押さえる「リモートアクセス」や、サービスプロバイダ等にデータを記録・印刷させて差し押さえる「記録命令付差押え」が行われます。
- 身体に対する強制処分: 覚せい剤事件での強制採尿や、飲酒運転事件での強制採血は、捜索差押許可状や身体検査令状を用い、医師が医学的に相当な方法で行うことを条件として実施されます。被疑者が同行を拒む場合は、採尿場所等まで連行することも許可されます。
6. 夜間執行の制限
私生活の平穏を守るため、日出前または日没後(夜間)に住居等に立ち入って捜索を行うには、令状に「夜間でも執行できる」旨の付記が必要です。ただし、自動車内や人の着衣に対する捜索など、私生活の平穏を害するおそれが低い場合には、夜間執行の許可は不要とされるのが一般的です。
自首のメリットと効果
自首(罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら進んで犯行を申告し、その処分に服すること)を行うかどうかの判断基準について、メリットを解説します。
1. 身体拘束(逮捕・勾留)を回避できる可能性
自首を検討する最大の判断基準の一つは、逮捕や勾留といった身体拘束を避けられるかどうかです。
- 逮捕の必要性の低下: 逮捕状の発付には、罪を犯した疑いに加え、逃亡や罪証隠滅の恐れといった「逮捕の必要性」が求められます,。自ら出頭して犯行を認める自首は、捜査に協力する意思を示すものであり、「逃亡の恐れがない」と判断される有力な材料となります,。
- 在宅捜査への移行: 自首によって逮捕の必要性がないと判断されれば、身柄を拘束されない「在宅事件」として捜査が進められる可能性が高まります。これにより、仕事や学校などの社会生活を維持しながら手続を進めることが可能になります。
2. 起訴・不起訴の判断および刑事処分への影響
検察官が事件を起訴するかどうか、あるいはどのような形式で起訴するかを判断する際、自首の事実は大きな影響を与えます。
- 不起訴処分(起訴猶予)の獲得: 資料によれば、犯行を認めて自首した事案において、さらに被害者との示談が成立すれば、「訴追の必要性がない」として起訴猶予(不起訴)になる可能性が高まります。特に侮辱罪などの軽微な事件では、自首と謝罪の意向が不起訴に向けた強い説得力を持ちます。
- 略式命令への誘導: 起訴される場合でも、自首していれば、公開の裁判を避けて書面審査だけで罰金を納付して終了する「略式命令」で済む可能性が高くなります。
3. 裁判における量刑上のメリット
万一、公判(正式な裁判)になった場合でも、自首は法律上の刑の減軽事由となり得ます。
- 刑の裁量的減軽: 刑法第42条第1項により、自首した者の刑は減軽することができると定められています。実務上、自首は「真摯な反省(悔悟の情)」を示す客観的な証拠として重視されます。
- 執行猶予獲得の可能性: 覚せい剤取締法違反などの事案であっても、15年以上犯罪から遠ざかっていた者が自首して犯行を認めたようなケースでは、再犯防止に向けた強い意志と評価され、執行猶予付き判決を得るための重要な有利な情状となります。
4. 証拠の確保と供述の信用性
- 記憶が鮮明なうちの供述: 自首をする際、弁護人と相談してあらかじめ供述内容を整理し、「弁面調書(弁護人が録取した供述書)」などを作成しておくことで、後の取調べで供述が不当に変遷させられるのを防ぎ、一貫した主張として信用性を高めることができます。
- 客観的証拠の提出: 証拠隠滅を疑われないよう、自ら証拠(凶器や盗品、電磁的記録など)を提出することで、捜査への誠実な協力をアピールできます。
5. 罪種別の判断基準(侮辱罪・財産犯など)
- 侮辱罪(SNS等の中傷): 資料に掲載されている侮辱罪の事例集をみると、多くのケースが数万円から30万円の罰金・科料となっています。こうした事案では、自首をして速やかに示談交渉を行うことが、前科をつけない(不起訴にする)ための現実的な戦略となります。
- 窃盗などの財産犯: 被害が軽微で初犯の場合、自首して被害弁償を行うことが、刑事手続を早期に終わらせる鍵となります。
注意点と弁護人への相談
自首は、「捜査機関に発覚する前」に行わなければ法的な自首としての効力を持ちません。また、不用意に自首すると、弁護人のアドバイスを受ける前に自分に不利な供述調書を作成されてしまうリスクもあります。
そのため、自首を検討する際の最も重要な判断基準は、「まず弁護士に相談し、自首に伴う不利益(実刑の可能性など)を正確に把握した上で、適切な出頭のタイミングと方法を計画できるか」という点にあります。私選弁護人であれば、警察への出頭に同行し、その場で弁護人選任届を提出して不当な取調べを牽制することも可能です。
自首のデメリット
自首(罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自ら犯行を申告すること)は、身体拘束の回避や刑の減軽という大きなメリットがある一方で、刑事弁護の実務的な観点からは無視できない不利益やリスク(デメリット)も存在します。
1. 取調べにおける「不利な供述調書」作成のリスク
自首をする最大のデメリットは、弁護人の適切なアドバイスを受ける前に、密室での取調べによって自分に不利益な内容の供述調書(自白調書)が作成されてしまうことにあります。
- 事後的な修正の困難さ: 一度署名・押印してしまった供述調書の内容を、後の裁判で覆すことは極めて困難です。取調官がまとめた調書には、必ずまとめる側の意図や主観が入り込むため、被疑者の本意ではないニュアンスが含まれるリスクがあります。
- 自白の強要・利益誘導への脆弱性: 弁護人が立ち会わない状況で、「認めれば釈放してやる」「認めないと裁判で重くなる」といった取調官の説得や利益誘導に耐えきれず、事実と異なる自白をしてしまうおそれがあります。
- 不正確な記憶の証拠化: 記憶が曖昧なまま自首して供述すると、後から客観的な証拠(防犯カメラ等)と矛盾が生じた場合に「嘘をついている」と判断され、かえって信用性を失うことになりかねません。
2. 捜査範囲の拡大と「余罪」の発覚
自首をきっかけとして、捜査機関が当初把握していなかった事実や余罪まで捜査が及ぶことがあります。
- 事件の広がり: 特定の行為について自首したつもりでも、取調べの過程で他の関連する行為や余罪について追及を受け、結果として起訴される事実が増えたり、刑罰が重くなったりする可能性があります。
3. 法的な「自首」として認められない可能性
すべての出頭が法的な意味での「自首」になるわけではありません。
- 「発覚前」の要件: 刑法上の自首による刑の減軽を受けるには、「捜査機関に発覚する前」に行う必要があります。すでに警察が被疑者を特定している場合、自ら出頭してもそれは単なる「任意出頭(出頭)」として扱われ、法的な減軽の恩恵が得られない場合があります。
4. 身体拘束(逮捕・勾留)を完全に回避できるわけではない
自首をしたからといって、必ず在宅捜査(釈放)になる保障はありません。
- 逮捕の可能性: 事案が重大である場合や、共犯者との口裏合わせが疑われる場合などは、自ら出頭した直後に逮捕状が執行され、そのまま身体拘束を受けることもあります。
- 精神的・身体的負担: 逮捕・勾留されれば、社会生活から隔離され、勤務先からの解雇や学校の中退といった重大な社会的損失を被るリスクが現実化します。
5. 社会的・経済的リスクの早期確定
本来であれば捜査機関に発覚しなかった可能性のある事件や、被害者が告訴をためらっていた事件であっても、自首をすることで刑事手続が確実に開始され、前科がつくリスクや社会的信用の失墜が確定してしまいます。
弁護活動における対策
これらのデメリットを最小限にするため、実務では以下の対応が推奨されています。
- 自首前のリーガルアドバイス: 警察へ行く前に弁護人と面談し、供述内容を整理した上で「供述書」を作成し、確定日付を得ておくことで、後の取調べでの変遷を防ぎます。
- 弁護人の同行: 私選弁護人が警察署への出頭に同行し、不当な取調べが行われないよう牽制することが有効です。
結論として、自首は有利な情状になり得ますが、事前の準備なく行うことは、捜査機関に対して一方的に有利な武器(証拠)を与えてしまうという大きな戦略的リスクを伴います。
告訴のポイント
「警察が刑事告訴を受理しない…」泣き寝入りしないための3つのポイント
「犯罪の被害に遭ったので、犯人を処罰してほしい…」その一心で警察署に駆け込んだのに、「これは事件化が難しい」「民事の問題だから」などと言われ、話すらまともに聞いてもらえなかった。
そんな悔しい経験をした方、あるいはこれから告訴を考えているが不安だという方は少なくないでしょう。
ポイント1:警察が告訴の受理を渋る「本音」 
まず、なぜ警察が告訴の受理に消極的なのか、その背景を知ることが対策の第一歩です。
- ① 捜査の負担が増える 刑事告訴を受理すると、警察は必ず捜査を開始する義務を負います。現場検証、聞き込み、証拠集め、書類作成…と、膨大な時間と労力がかかります。警察も人手不足であり、多忙な業務の中で、立件・起訴まで持ち込むのが難しそうな案件に時間を使いたくない、というのが正直なところです。
- ② 検挙率への影響 捜査をしても犯人を逮捕できなかったり、証拠不十分で検察が不起訴(起訴しないこと)にしたりすると、その事件は「未解決」扱いになります。警察組織としては、検挙率(事件を解決した割合)が評価に影響するため、最初から勝算の低い事件は避けたいというインセンティブが働きます。
- ③ 「民事不介入」の原則 「お金を貸したのに返してくれない」「契約トラブル」といった個人間・企業間の金銭トラブルに対し、警察は「民事不介入」という原則を持っています。つまり、「それは当事者同士の話し合いか、民事裁判で解決すべき問題で、警察が介入することではありません」というスタンスです。詐欺罪など犯罪に該当する可能性があっても、まずこの原則を理由に、受理を断ろうとするケースが非常に多いです。
ポイント2:実は警察に「受理する義務」がある 
警察の「本音」は上記のとおりですが、法律上、警察には原則として告訴を受理する義務があります。 これはあなたの権利として、強く知っておくべきことです。
根拠となるのは「犯罪捜査規範」という警察の捜査活動のルールを定めた規則です。
犯罪捜査規範 第63条1項 司法警察員たる警察官は、告訴、告発又は自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
また、過去の裁判例でも、「捜査が困難であるとか、被疑者が起訴される見込みが少ないといった事情は、告訴を受理しない理由にはならない」とはっきり示されています。
つまり、警察が受理を拒否できるのは、
- そもそも内容が「明白に」犯罪に当たらない
- 公訴時効が成立している
- 告訴できる人(被害者本人など)ではない
といった、およそ告訴の要件を形式的に満たしていない明白なケースに限られます。「証拠が弱い」「民事の問題っぽい」といった理由は、本来、受理を拒む正当な理由にはならないのです。
ポイント3:こうすれば受理されやすい!3つの具体策 
「受理義務がある」と言っても、ただ口頭で訴えるだけでは、のらりくらりとかわされてしまう可能性が高いです。受理させるためには、警察が「これは捜査せざるを得ない」と判断するような「お膳立て」をして、戦略的に臨むことが極めて重要です。
- ①「告訴状」という書面を作成・持参する 口頭での相談ではなく、「告訴状(こうそじょう)」という正式な書面を作成して提出しましょう。誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、何を(What)、どのように(How)被害を受けたのか、事実関係を時系列で分かりやすく整理し、どの行為がどの法律(刑法〇〇条違反など)に触れるのかを明記します。これにより、あなたの「本気度」が伝わり、警察も無視できなくなります。
- ② 証拠を可能な限り集め、整理しておく 警察が最も嫌がる「捜査の手間」を、こちらでできるだけ減らしてあげることが重要です。
- メール、LINEのやり取り
- 契約書、念書
- 音声の録音データ、動画
- 被害状況の写真
- 関係者の連絡先リスト これらの証拠を時系列に沿って整理し、告訴状と一緒に提出することで、犯罪の客観的な裏付けとなり、警察も事件の全体像を把握しやすくなります。
- ③ 弁護士に相談し、同行してもらう 最も効果的な方法が、弁護士に依頼することです。弁護士が作成した告訴状は、法的な要件を確実に満たしているため、警察も形式的な不備を理由に断ることができません。さらに、弁護士が警察署へ同行することで、警察に対する強力なプレッシャーとなります。担当者が不当な理由で受理を拒もうとしても、弁護士がその場で法的な根拠を示して反論するため、受理される可能性が飛躍的に高まります。実際に、告訴に慣れた弁護士が対応して受理されないケースは殆ど皆無といっても良い状況です。
まとめ
刑事告訴は、残念ながら「ただ行けば受け付けてくれる」というものではないのが現実です。しかし、警察が受理を渋る理由を理解し、「①告訴状の作成」「②証拠の整理」「③弁護士に依頼する」という対策をしっかり行うことで、その壁を乗り越えることは十分に可能です。
もしあなたが犯罪の被害に遭い、本気で犯人の処罰を望むなら、決して泣き寝入りせず、これらの準備を整えて、あなたの正当な権利を主張してください